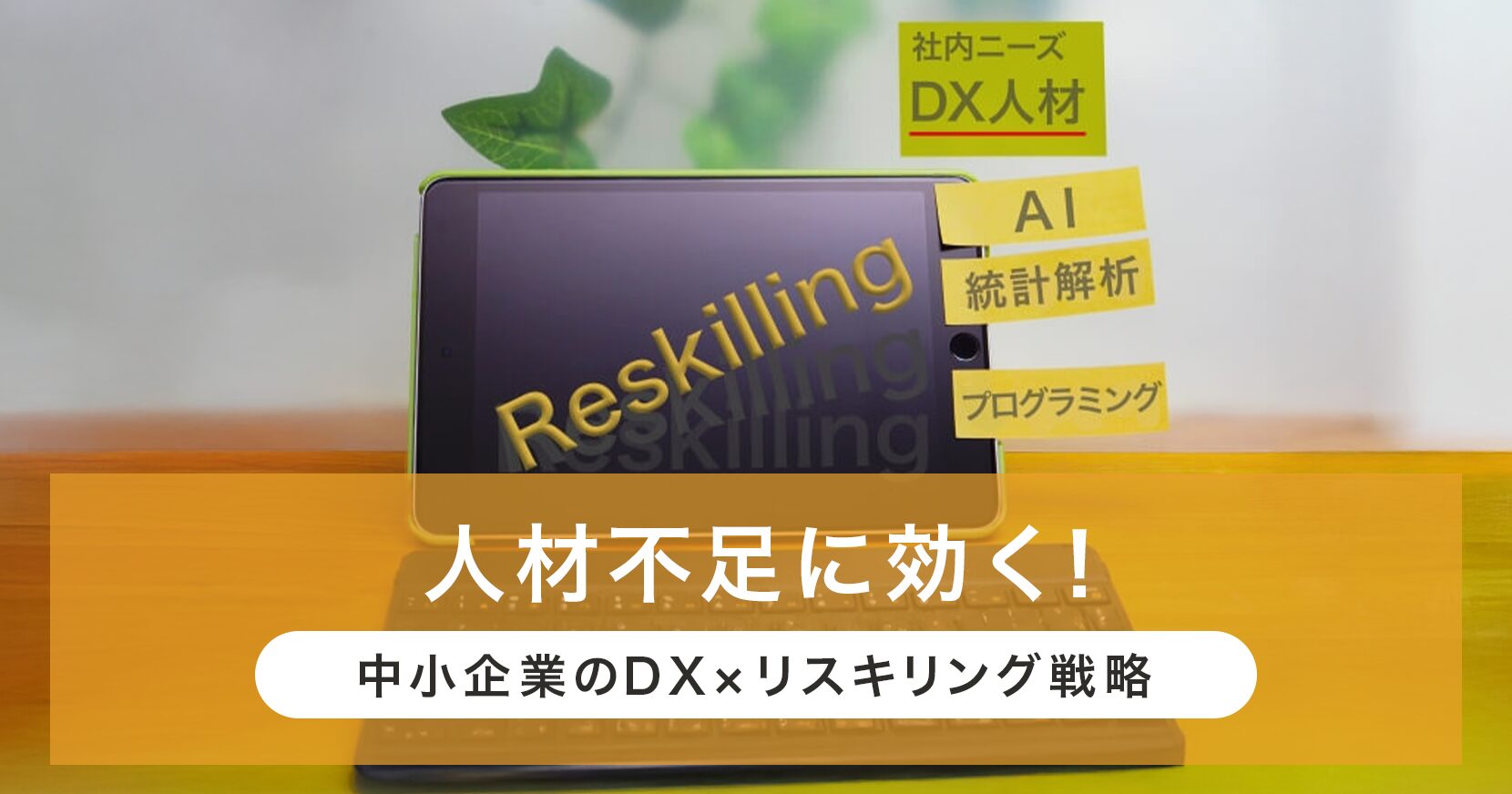目次
急速に進展するデジタル化の波により、多くの中小企業が「人材不足」と「DX推進」という二重の課題に直面しています。現場ではITスキルを持った人材の採用が難しく、社内にノウハウも乏しいという声が増えているのが現状です。
ここでは、こうした課題を打破する鍵となる「リスキリング」とは何かを解説し、DX時代に求められるスキルや、企業が取り組むべき育成戦略、助成金の活用方法まで具体的に紹介します。
読み進めることで、自社に最適な人材育成計画が見えてきて、業績向上に直結するヒントが得られるはずです。
そもそもリスキリングとは何か?DX時代に必要とされる背景
DX(デジタルトランスフォーメーション)が急速に進行する中、企業に求められるのは新しい業務への対応力です。これを支えるのが「リスキリング」、つまり既存の従業員に新たなスキルを習得させ、変化に対応できる人材に育てる取り組みです。
ここでは、リスキリングの基本概念や他の教育施策との違い、そしてDX推進との関係について詳しく解説していきます。
リスキリングの定義と注目される背景
リスキリングとは、既存の職務ではなく、将来の職務に対応するためのスキルを再習得することを指します。単なるスキルアップや研修とは異なり、業務構造や社会の変化に対応するための再教育に位置付けられます。
注目を集める背景には以下のような要因があります。
- DXの加速により、新しい技術や業務フローに対応できる人材が不足している
- 少子高齢化や労働人口の減少で即戦力人材の採用が困難
- 国がリスキリングを含む中小企業の人材開発支援制度を積極的に後押ししている
こうした流れを受けて、多くの企業が自社人材の再活用に注目し始めています。
リカレント教育・アンラーニング・OJTとの違い
リスキリングとよく比較されるのが、リカレント教育・アンラーニング・OJTです。以下の表でその違いを明確にしましょう。
| 施策名 | 内容 | 目的 | 適用場面 |
|---|---|---|---|
| リスキリング | 新しい職務に対応するためのスキル再習得 | 業務の変化に対応 | DX推進、新規事業など |
| リカレント教育 | 学び直し(主に大学や専門機関) | 知識のアップデート | キャリア中盤〜後半 |
| アンラーニング | 古い知識・価値観の捨て直し | マインドセットの転換 | 組織文化の改革 |
| OJT | 現場での実務教育 | 即戦力育成 | 日常業務内での教育 |
リスキリングは特に変革期における人材戦略の中核として機能します。
DX推進におけるリスキリングの役割とは
DXを推進するには、テクノロジーを理解し使いこなせる人材の存在が欠かせません。しかし、そのすべてを外部採用で賄うのは非現実的です。そこで重視されるのが、社内人材をDX人材へと変革させるリスキリングの重要性です。
具体的な役割としては以下のような点が挙げられます。
- 業務プロセスの自動化を担うAI・RPAツールの操作を社内で行えるようにする
- デジタルマーケティングやデータ分析の基本的なスキルを内製化する
- 従業員のキャリア意識を変革し、DXへの抵抗感を軽減する
つまりリスキリングは、DX成功のための土台を築く取り組みとして、今後ますます重要性を増していくと言えるでしょう。
なぜ今、中小企業にリスキリングが必要なのか

人材不足が常態化する中小企業では、業務のDX化を進めたくても「動かせる人材がいない」という課題が浮き彫りになっています。加えて、限られた予算や時間の中で即戦力を確保することが難しいため、社内人材の再教育であるリスキリングが現実的な解決策として注目を集めています。
ここでは、中小企業が直面する課題とリスキリングによるメリットについて解説します。
人材不足・採用難の現場における現実的な解決策
中小企業では特に「人材がいない」「採用しても定着しない」という問題が深刻です。地方や特定業界では、応募すら来ないというケースも珍しくありません。
こうした状況では、新規採用よりも社内人材の能力再開発(リスキリング)に注力するほうが現実的です。すでに業務を理解している従業員を新たな業務に対応させることで、以下のような利点が得られます。
- 採用コストや教育コストの削減
- 現場に精通した人材がすぐに新しい役割で動ける
- 従業員のモチベーション向上や離職防止にもつながる
つまり、リスキリングは中小企業にとって「人材確保」そのものの代替手段となり得るのです。
DX推進に必要なスキルを外部に頼らず内製化できる
デジタル技術の活用がビジネス競争力を左右する現代において、内製化は重要なキーワードです。外部委託は便利な一方で、コスト負担が大きく、ノウハウが社内に蓄積されにくいというデメリットもあります。
そこでリスキリングを通じて、以下のようなスキルを社内に根付かせることが注目されています。
- Excel業務の自動化(マクロやRPA)
- SEOや広告運用、SNS運用などのWEBマーケティング
- 業務改善ツール(Notion、Slackなど)の利活用
このように、ノウハウを外に出さず「社内で完結できる体制」を作ることが、企業の持続的成長に直結します。
従業員の成長が業務効率化と利益に直結する理由
リスキリングを通じて従業員が新しいスキルを習得すると、業務の無駄が減り、生産性が向上します。これは中小企業にとって「即戦力の育成」と同義です。たとえば、製造業においてITリテラシーの低い現場職がタブレットで工程管理をできるようになることで、業務の効率化につながるケースなどが考えられます。
リスキリングによって、以下のような成果が期待できます。
- 作業時間の短縮=人件費の削減
- 顧客対応のスピード向上=顧客満足度の向上
- 従業員のスキル向上=キャリア自律の促進
このように、従業員の成長が業務効率化と企業利益にダイレクトに結びつくのが、リスキリングの大きな強みです。
DX時代に必要なスキルの具体例とリスキリング施策
DXが進む中、求められるスキルは単なるITリテラシーではなく、業務の自動化やデジタル活用を実践的に行える能力です。中小企業では、限られたリソースの中でこうしたスキルをいかに獲得・活用していくかが重要です。
ここでは、DX推進に直結する具体的なスキルと、それを社内に根付かせるためのリスキリング施策を紹介します。
AI・RPAなど自動化ツールの理解と操作スキル
DXの中心となるのが、業務自動化による効率化です。AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、人手に頼らない業務の自動化を実現するためのツールです。
具体的に必要なスキル例
- RPAツール(例:UiPath、Power Automate)での業務フロー作成
- 簡単なPythonスクリプトによる自動化処理
- ChatGPTなどAIツールの業務活用法の理解
これらを現場で使いこなすことで、ルーチン作業から解放され、生産性が飛躍的に向上します。まずは現場に導入しやすいツールから始めることで、抵抗感なく取り組めるようになります。
SEO・WEB広告・データ分析などのマーケティングスキル
デジタル時代の集客に欠かせないのが、WEBマーケティングのスキルです。特に中小企業では、なるべくコストをかけずに効果を出す手法として、SEO対策やWEB広告運用の内製化が重要視されています。
身に付けたいスキル領域
- Googleアナリティクスやサーチコンソールによるデータ解析
- キーワード調査とコンテンツ設計
- リスティング広告やSNS広告の運用ノウハウ
これらは業者に任せるだけでは効果が見えにくいため、社内で運用スキルを獲得することで、PDCAサイクルを高速で回すことが可能になります。
人的資本経営とキャリア自律に必要な思考・行動力
DX人材の育成には、スキルだけでなくマインドセットの変革も重要です。特に人的資本経営が注目される今、自律的にキャリアを考え行動できる人材が求められています。
強化したい力
- 自ら課題を設定し解決策を考える「課題発見力・問題解決力」
- 上司や他部署との円滑な連携を図る「コミュニケーション力」
- 変化に柔軟に対応できる「レジリエンス」
これらは研修だけでなく、現場でのOJTやフィードバック機会を通じて育成していく必要があります。経営層も一体となった人材開発体制が成功のカギを握ります。
リスキリング導入のステップと社内推進のコツ

リスキリングを成功させるには、単に研修を行うだけでなく、全社的な計画と現場定着の設計が必要です。とくに中小企業では、経営資源に限りがあるため、計画的な導入と社内の巻き込みが重要となります。
ここでは、効果的な導入プロセスと現場で推進するためのコツを紹介します。
スキルマップと事業課題を照らし合わせて設計する
リスキリング計画の出発点は、「何をどこまで習得させるのか」を明確にすることです。そのために役立つのがスキルマップの作成です。
スキルマップ作成の手順
- 現状の従業員のスキルを可視化
- 自社のDX戦略・事業課題と照らし合わせて、必要スキルのギャップを洗い出す
- 優先順位を決めて研修対象・内容を決定
これにより、「誰に」「どんなスキルを」「どの時期に」身につけてもらうかが明確になり、成果に直結しやすい研修設計が可能になります。
教育プログラムは業務直結型+実践型がカギ
研修内容は、業務に直結した実践型の学習設計が成功の鍵です。座学だけでは「学んだつもり」で終わることが多く、定着にはつながりません。
効果的な教育設計のポイント
- 具体的な業務課題をもとにケーススタディやプロジェクト演習を組み込む
- 日々の業務の中でツールやスキルを活用する機会を設ける
- 研修後に発表やレポート提出などのアウトプット機会を設ける
特に中小企業では、現場との距離が近いため、現場業務を教材に活用する形での研修が非常に効果的です。
習得したスキルを定着させる運用設計と評価制度
リスキリングを制度として根付かせるには、研修後の定着と評価の仕組みが欠かせません。学んだ内容を現場で継続的に活かせるよう、以下のような工夫が求められます。
スキル定着のための仕組み
- スキル活用を評価制度に反映
- 社内で勉強会・事例共有の機会を設ける
- 上司が習得状況を把握し、支援できる仕組みを整備する
こうした運用設計により、単発的な研修で終わることなく、「学び続ける文化」が社内に根付き、組織全体のDX推進力が向上します。
リスキリングでつまずかないための課題と解決策
リスキリングは中小企業のDX化を推進する上で有効な手段ですが、導入や運用の過程ではいくつかの壁にも直面します。
ここでは、現場で起こりがちな課題とその解決策を紹介します。あらかじめつまずきやすいポイントを把握しておくことで、円滑なリスキリングの実行が可能になります。
中高年社員の意識が上がらない問題への対処法
リスキリングの現場で特に多いのが、中高年社員の学習意欲の低下です。「今さら学び直すのは…」「自分には関係ない」と感じてしまうケースも珍しくありません。
こうした意識を変えるには、役割の再設計と動機づけが重要です。
- 成果が見える業務への再配置(例:RPA導入のリーダーに任命)
- 過去の経験を活かせる分野のリスキリング(例:マネジメント層には人的資本経営の研修)
- 個別面談でキャリアビジョンと研修の関係性を明確にする
意欲を引き出すには、「必要だから受けさせる」ではなく、「自分のキャリアにプラスになる」という実感を与えることが大切です。
「学ぶだけ」で終わらせない実務連動の仕掛け
研修を実施しても、「学んだ内容が業務で活かされていない」という悩みは多く聞かれます。これを防ぐためには、研修と実務を連動させる仕組みが必要です。
実務との接続方法の例
- 研修後のプロジェクト参画(例:Web広告運用の研修後、社内で月次広告分析を担当)
- 研修内容をもとに小規模な改善活動を実施させる
- 成果報告会を設けて、スキル活用を全社で共有
学びを“仕事の一部”とすることで、知識が実行力に転化しやすくなります。
外部リソースや制度を賢く活用する視点
リスキリングには時間とコストがかかるため、外部のリソースを活用する視点も欠かせません。
特に専門性が求められる分野では、社内だけで完結しようとせず、外部の研修・制度を組み合わせるのが効果的です。
活用できる外部リソースの例
- 専門機関のオンライン講座(例:DX、AI、SEO)
- 助成金制度の活用(人材開発支援助成金など)
- 教育事業者による現場連動型研修
こうした支援を利用することで、コストを抑えつつ質の高いリスキリングが可能になり、導入のハードルを下げることができます。
費用を抑えたい場合は助成金の活用も検討しよう

中小企業がリスキリングに取り組む際、最も大きな障壁となるのが「研修コスト」です。予算が限られる企業にとって、外部研修や社内教育に多額の費用を投じるのは簡単なことではありません。そこで活用したいのが「人材開発支援助成金」などの助成金制度です。
ここでは、助成金の概要と対応範囲、申請のコツを紹介します。
従業員のリスキリングに活用できる「人材開発支援助成金」の概要
「人材開発支援助成金」は、厚生労働省が企業の人材育成やスキル転換を促進する目的で設けている制度です。条件を満たせば、研修にかかる経費の一部と、受講時間に応じた賃金の一部が助成対象となります。
特に「事業展開等リスキリング支援コース」は、企業が新たな事業展開や業務転換を行う際に、従業員へ必要なスキルを習得させるための訓練に対して助成が受けられる仕組みです。
主な特徴は以下の通りです。
- デジタル・DX人材育成にも対応(AI・SEO・広告運用などの研修も対象となるケースあり)
- eラーニングやオンライン講座も対象に含まれる
- 助成額上限:1事業所あたり1年度あたり1億円(助成率:中小企業は経費75%、賃金960円/時)
費用を抑えながら戦略的なリスキリングに取り組みたい企業様にとって、有効な支援制度となっています。
リスキリング・DX・マーケ支援にも幅広く対応可能
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、単なるスキル研修に限らず、幅広い分野のDX・マーケティング関連施策にも活用可能です。たとえば以下のような内容が支援対象になります。
- SEO対策等のWebマーケティング研修
- AI・RPAなどの自動化ツールの活用講座
- 広告運用スキルのインハウス化支援
- データ分析やDX戦略構築のための研修プログラム
これらの研修についても条件を満たしていれば助成対象となる可能性があります。
申請のステップと失敗しないための注意点
助成金の申請にはいくつかの手続きが必要であり、計画的な準備が不可欠です。以下は申請の流れと注意点です。
申請の基本ステップ
- 事前準備:
- 職業能力開発推進者の選任
- 事業内職業能力開発計画の作成・周知
- 計画届の提出:
- 訓練実施計画届(様式第1-1号)の提出
- 提出期限:訓練開始日の6か月前から1か月前までの間
- 研修実施:
- 計画に沿った訓練の実施
- 出席記録等の管理
- 支給申請:
- 支給申請書の提出
- 提出期限:訓練終了日の翌日から起算して2か月以内
失敗しないためのポイント
- 事前申請を忘れず、期限に余裕を持って提出
- 助成対象となる研修かどうかを確認
- 受講記録や賃金支払い証明などエビデンス管理を徹底
面倒に見える申請作業ですが、支援に精通した外部パートナーに相談することで大きく効率化できます。
NBCインターナショナルのデジタル分野の研修/リスキリング支援のご案内

IT・DXの推進には、現場で実務を担う人材の育成が欠かせません。
NBCインターナショナルでは、SEO対策やWEB広告運用に関する研修プログラムを用意しています。現役のコンサルタントが講師を務め、eラーニングやZoom研修により、最新の知識と実践力がバランスよく習得できる構成です。
人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで受講費用の約80%が助成対象となります。
以下に各講座の概要をご紹介します。
WEBサイトのデジタル分析技術習得講座
Webサイトの検索順位や成果改善につなげるための、内部対策・サイト解析の実践知識を体系的に習得できる講座です。
検索エンジンの仕組みや構造化データなどの基礎から、GA4やSearch Consoleなどを活用した分析・改善スキルまでを段階的に学べます。
- 内部対策の基礎/応用
- サイト解析と改善実践
- 検索順位低下の原因分析と対応策
習得できるスキル例:
- 検索エンジン最適化の構造的理解
- 内部対策の実践ノウハウ
- 最新のウェブ指標と分析ツール活用法
AIを活用したWEBコンテンツ制作のDX化講座
生成AIツールを活用して、SEOコンテンツ制作を効率化・高度化させるスキルを習得する研修です。
キーワード調査から記事構成、ライティング、アップロードまでを一貫して学び、AIを使ったライティング・リライト手法も実演で体得できます。
- コンテンツSEOの基礎〜実演
- AIツールを用いた制作DX
- キーワード選定やペルソナ設計の手法
習得できるスキル例:
- AIツールによるコンテンツ制作効率化
- ターゲットニーズに応える記事設計
- 実践的なキーワード選定・リライト技術
デジタルマーケティング運用・分析導入による販促DX化講座
広告配信の最適化とデータ分析による販促効果の最大化を目指す企業向け研修です。
リスティング広告・メタ広告の基礎から運用実演、分析による改善手法までを網羅し、広告運用人材の社内育成を目指す企業に最適です。
- リスティング・メタ広告の基礎/応用
- デジタル広告の効果検証と改善実践
- 最新の運用ツールを活用した販促DX
習得できるスキル例:
- 社内での広告運用体制の内製化
- データドリブンな広告改善スキル
- 広告ツールの活用による競争力強化
まずは資料ダウンロード・無料相談からご検討ください
NBCインターナショナルの研修は、SEOや広告運用のノウハウを社内に蓄積し、外注に頼らず自社でマーケティングを改善できる体制づくりを支援する実践型プログラムです。自社の担当者がスキルを習得することで、継続的な集客改善や施策のPDCAを自社内で回せるようになります。
また、人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで、条件を満たせば受講費用の約80%が助成されるため、コストを抑えながら社内人材の育成を進めることも可能です。
資料ダウンロードや無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
中小企業が抱える人材不足やDXの遅れといった課題に対して、「リスキリング」は最も現実的で効果的な解決策の一つです。社内の既存人材に新たなスキルを習得させることで、業務の効率化、利益向上、そして人材の定着につなげることが可能になります。
ここでは、DX時代に求められるスキルや実践的なリスキリング施策、さらには費用の壁を乗り越えるための助成金制度についても具体的に解説しました。中でも、費用の約80%が支援される「人材開発支援助成金/事業展開等リスキリング支援コース」は、中小企業にとって非常に強力な味方です。
人材育成と事業成長の両立を目指す企業にとって、今こそがリスキリングに踏み出す絶好の機会です。
※本記事は助成金の受給を保証するものではありません。各助成金制度の内容・申請条件等は、公式サイト等で最新の情報をご確認ください。