目次
中小企業のWeb担当者や経営者の中には、「検索順位が上がらない」「どんなキーワードを設定すればいいのかわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。SEO対策の第一歩となるのが、検索キーワードの適切な設定です。
本記事では、初心者でも実践できるキーワード選定の基本から、ホームページでの効果的な配置方法、避けるべき落とし穴、改善の進め方までを体系的に解説します。正しいキーワード設計を学ぶことで、検索エンジンにもユーザーにも見つけられやすいサイトを目指せるようになります。
検索キーワード設定の基礎を理解する
検索キーワードを設定する際は、まず「なぜその作業が必要なのか」「どのような役割を果たすのか」を理解しておくことが大切です。基本をしっかり押さえることで、その後の選定や配置もスムーズになり、SEO効果を最大限に引き出すことができます。ここでは、検索キーワードの基本的な定義とSEOにおける役割について解説します。
検索キーワードとは何かを初心者向けに解説
検索キーワードとは、ユーザーがGoogleなどの検索エンジンに入力する言葉やフレーズのことを指します。たとえば「ホームページ 集客 方法」「飲食店 SEO」などがそれにあたります。
これらのキーワードは、ユーザーがどんな情報を求めているのかを示す“意図”の表れでもあります。したがって、ホームページを作成する際には、自社の商品やサービスに関連するキーワードを適切に設定することが重要です。
検索キーワードは主に次のように分類されます。
- ビッグキーワード:検索ボリュームが多く、競合も多い(例:ホームページ)
- ミドルキーワード:ある程度絞られていて、検索数も中程度(例:ホームページ 集客)
- ロングテールキーワード:ニッチで具体的な検索語(例:中小企業 ホームページ 集客 方法)
初心者はまず、ロングテールキーワードを中心に設計することで成果が出やすくなります。
SEOにおけるキーワード設定の役割とは
SEOにおける検索キーワードの設定は、単なる「言葉選び」ではありません。検索エンジンに「このページはこの内容について書かれている」と伝える重要な手段です。
適切なキーワードがページ内に配置されていれば、Googleはそのページを「このキーワードで検索する人にとって有益」と判断しやすくなります。
また、キーワードはユーザーのニーズとページ内容をつなぐ橋渡し役でもあります。次のような役割を果たします。
- 検索順位に影響を与える
- ユーザーにとっての“見つけやすさ”を高める
- コンテンツ設計の方向性を定める
SEO初心者の多くは、コンテンツばかりに意識が向きがちですが、土台となるキーワード設計が不適切だと、どれだけ良質な情報でも見つけてもらえません。そのため、検索キーワードの理解と設定はSEO対策の出発点として極めて重要です。
ホームページに効果的なキーワードを選定する方法
検索上位を狙うためには、適当にキーワードを選ぶのではなく、ターゲットユーザーの検索意図を読み取り、戦略的にキーワードを選定することが重要です。ここでは、ユーザー理解に基づく選定方法と、競合を避けつつ成果を出すためのロングテール戦略まで、実践的なアプローチを解説します。
ターゲットユーザーと検索意図の明確化
SEOで成果を上げるには、「誰に向けて」「どんなニーズを解決するために」ホームページを作るのかを明確にすることが第一歩です。キーワード選定もこの原則に従って行うべきです。
【ターゲットと検索意図を整理する手順】
- ターゲット像を具体化する
例:「自社のサービスを必要とする中小企業の経営者」「地域密着型の店舗オーナー」など。 - ターゲットの課題や悩みを洗い出す
例:「ホームページを作ったけれど全く集客できていない」「どんなページを作ればいいか分からない」など。 - 検索するであろう言葉を想像する
例:「ホームページ 集客 方法」「店舗 ホームページ 作り方」など。
これらを整理した上で、検索ボリュームや競合性も踏まえてキーワードを選ぶと、より効果的に検索上位を狙えるようになります。
関連キーワードとロングテールキーワードの活用
検索意図に合致したキーワードを選ぶためには、メインキーワードだけでなく、関連語やロングテールキーワードの活用が重要です。ロングテールとは、検索ボリュームが少なくても、具体的で購買や問い合わせにつながりやすいキーワード群のことです。
【ロングテールキーワードを見つける方法】
- Google検索のサジェストを活用する
入力途中に表示される候補は、実際に検索されている言葉のヒントになります。 - ラッコキーワードやGoogleキーワードプランナーを使う
無料ツールで関連キーワードの洗い出しが可能です。 - 実際のアクセスデータをもとに追加する
サーチコンソールで過去に検索されたワードから、成果につながりそうなキーワードを掘り出します。
例えば、「ホームページ 集客」よりも、「美容室 ホームページ 集客 方法」「BtoB ホームページ 問い合わせ 増やす」といったロングテールキーワードの方が、意図が明確でCV(コンバージョン)にもつながりやすいです。
ロングテールを意識した設計にすることで、競合が少ないニッチな層からのアクセスを効果的に獲得できます。
検索キーワードをホームページに効果的に配置する
適切なキーワードを選定できたとしても、ホームページ内の適切な位置に配置できなければ、その効果は十分に発揮されません。検索エンジンはコンテンツ内の構造やテキストの使われ方からページのテーマを判断しています。ここでは、検索順位に影響を与える重要なエリアへのキーワードの正しい入れ方を解説します。
タイトルタグとメタディスクリプションへの設定方法
タイトルタグ(titleタグ)とメタディスクリプションは、検索結果に表示される最も重要な要素です。ここにキーワードを適切に含めることで、クリック率(CTR)や検索順位にも好影響を与えます。
【タイトルタグのポイント】
- キーワードはタイトルの前方に配置する
例:「ホームページ 集客 方法|中小企業向けSEOガイド」 - 32文字前後に収める
長すぎると検索結果で省略されてしまいます。 - ユーザーが「読みたくなる」文言を意識する
「完全ガイド」「初心者向け」「○選」などの言葉を組み合わせると効果的です。
【メタディスクリプションのポイント】
- 80~120文字を目安に、主要キーワードを自然に含めます。
- 検索意図に答える内容であることを示す。
- CVへの導線となる価値提案を含める。
たとえば:「自社ホームページの集客力を高めたい中小企業のために、SEO初心者でも実践できるキーワード設定法を徹底解説します。」
検索結果上でのクリック率向上は、間接的にSEO評価にもつながるため、タイトルとディスクリプションへのキーワード配置は非常に重要です。
見出しタグや本文内での自然な使い方
見出しタグ(h1〜h3)や本文内でのキーワード使用は、検索エンジンにテーマを伝えるだけでなく、ユーザーにとっても情報の整理に役立ちます。ただし、不自然に詰め込むのではなく、文脈に沿って使うことが大切です。
【見出しタグの使い方】
- h1には1ページに1つ、メインキーワードを自然に入れる
- h2、h3には関連キーワードやロングテールキーワードを活用
- 見出し自体が簡潔で内容を端的に表していること
【本文内でのキーワード使用のポイント】
- 段落ごとに1回程度、過剰な繰り返しは避ける
- 読者にとって自然に読める言い回しにする
- 同義語や言い換え表現も活用し、冗長にならないように工夫する
例えば、「SEO キーワード 入れ方」というキーワードを使う場合でも、「SEOで成果を上げるには、キーワードの入れ方が重要です」と自然に言い換えることで読みやすさとSEO効果を両立させることができます。
このように、キーワードはページ全体の構造を意識しながら、読者ファーストで配置していくことが、成果につながるコンテンツ作りのポイントです。
避けるべきキーワード設定の失敗パターン
せっかく検索キーワードを設定しても、やり方を間違えると逆効果になる場合があります。特にSEO初心者が陥りやすいのが、キーワードの「詰め込み」や「曖昧な選定」です。こうした誤りを回避することが、長期的に安定した検索流入とCVR向上につながります。ここでは、失敗につながる具体的な例と、その改善方法を解説します。
キーワード詰め込みとそのSEOへの悪影響
「とにかくキーワードをたくさん入れれば順位が上がる」と思っている方は要注意です。過剰なキーワード使用は、Googleからスパムと見なされ、評価を落とす原因になります。
【キーワード詰め込みの典型例】
- 同じキーワードを1文中に何度も使う
例:「SEOキーワードの設定はSEOキーワードの順位に影響するSEOキーワードの基本です」 - 不自然な語順でキーワードを差し込む
例:「ホームページ検索キーワード設定する方法を初心者設定が簡単に設定可能」
こうした文章は読みにくく、ユーザー体験(UX)も悪化します。その結果、滞在時間が短くなり、直帰率が増えて、SEOにも悪影響を与えます。
【対策方法】
- 1つのキーワードは段落内に1回程度を目安にする
- 同義語や自然な言い換えで表現の幅を広げる
- 文章の読みやすさを常に優先する
SEOは「検索エンジンのための施策」ではなく「ユーザーのための情報提供」であることを忘れないようにしましょう。
曖昧なキーワード選定がもたらす機会損失
キーワードが曖昧すぎると、ユーザーの検索意図とページの内容が合わなくなり、成果につながりません。また、検索ボリュームが多い割に競合が激しいキーワードを選ぶと、上位表示が難しくなり機会を失う原因にもなります。
【よくある曖昧なキーワードの例】
- 「情報発信」「サービス向上」「効果的」など、具体性に欠ける言葉
- 「ホームページ」など、単体では意味が広すぎるワード
曖昧なキーワードを使ってしまうと、Googleもそのページをどう評価すべきか判断しづらく、検索結果にも出にくくなります。
【改善のポイント】
- 「誰に・何を・どうしたいか」を具体化したキーワードに変える
例:「ホームページ」→「歯科医院 ホームページ 集客 方法」 - 検索ボリュームと競合性を事前に調査する
キーワードプランナーやUbersuggestなどのツールを活用すると効果的です。
明確で具体的なキーワード設計を行うことが、SEO成果を出すための第一歩です。
成果を上げるためのキーワード設定の改善手順

一度キーワードを設定したからといって、それで終わりではありません。検索ニーズや競合状況は日々変化しており、それに応じた改善と検証が必要です。ここでは、Googleサーチコンソールやアクセス解析ツールを使って、キーワード設定の効果を可視化し、PDCAを回すための手順を解説します。
Googleサーチコンソールで効果を検証する
Googleサーチコンソールは、自社ホームページがどんな検索キーワードで表示されているか、どのくらいクリックされているかを確認できる無料ツールです。これを活用することで、現状のキーワード設定が成果につながっているかを定量的に把握できます。
【チェックすべき主な項目】
- 検索クエリごとの表示回数とクリック数
- 平均掲載順位
- クリック率(CTR)
【改善のポイント】
- CTRが低い場合:タイトルやメタディスクリプションを見直す
- 掲載順位が低い場合:コンテンツの質やキーワードの使い方を改善する
- クリック数が少ないが表示回数が多い場合:検索意図とページ内容にズレがないかを見直す
特に、「意図しないキーワード」での流入が多い場合は、ページ内容とキーワードの整合性を調整する必要があります。こうした分析により、効果的なキーワードとそうでないものを見極めることができます。
アクセス解析をもとにPDCAを回す方法
キーワード設定が成果につながっているかを判断するには、Googleアナリティクス4(GA4)などのアクセス解析ツールと組み合わせて、ユーザー行動もあわせて見ることが重要です。GA4は、旧バージョン(ユニバーサルアナリティクス)が2024年7月1日に完全にサポート終了したことに伴い、現在の標準ツールとなっています。
【見るべきユーザーデータ】
- エンゲージメント率の低いページ:検索意図に合っていない可能性が高い
※GA4では直帰率ではなくエンゲージメント率が指標となります - 平均エンゲージメント時間:コンテンツが適切に読まれているかの指標
- コンバージョン数:設定したキーワードでどれだけ成果につながっているか
【PDCAサイクルの実践例】
- Plan(計画)
「○○のキーワードからのエンゲージメント率が低い」→導線改善を計画 - Do(実行)
該当ページのCTAやコンテンツ構成を変更 - Check(検証)
アクセス解析で変更後の数値を確認 - Act(改善)
良い結果なら他ページにも展開、悪ければ別案を検討
このサイクルを定期的に繰り返すことで、キーワード設定の精度が高まり、安定した検索流入と成果が期待できるようになります。
検索エンジンとユーザー両方に好まれる設計を意識する
検索キーワードを適切に設定することは重要ですが、それだけでは不十分です。検索エンジンが評価しやすく、かつユーザーが使いやすい設計にすることが、SEOとCVR(コンバージョン率)の両立に不可欠です。ここでは、UX(ユーザー体験)とE-E-A-Tの観点から、検索にもユーザーにも好まれるホームページ設計の考え方を解説します。
UXを意識したコンテンツと構造の最適化
ユーザーがストレスなく情報を得られる構造にすることで、離脱率が下がり、滞在時間やCVRが向上します。これはGoogleが評価するユーザー行動指標にも良い影響を与えるため、SEO的にも有利です。
【UX改善に向けた主なチェックポイント】
- 読みやすいレイアウト
適度な改行、見出しの使い分け、箇条書きの活用などで情報を整理する - ページ速度の最適化
表示速度が遅いとユーザーはすぐに離脱してしまいます。画像の圧縮やコードの最適化が有効です。 - スマホ対応(モバイルファースト)
スマートフォンでの閲覧が主流になっている今、レスポンシブデザインは必須です。 - 明確な導線とCTA
問い合わせや資料請求などの行動をスムーズに誘導できるボタン設計が必要です。
こうした構造の最適化を行うことで、ユーザー満足度とSEO評価を同時に高めることができます。
E-E-A-Tを踏まえたキーワード設計のポイント
Googleが重視する評価基準に「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」があります。この指標は、特に検索順位が重要なBtoBサイトや医療・金融などの領域で強く影響します。
【E-E-A-Tを意識したキーワード戦略のポイント】
- 実体験に基づいた情報発信(Experience)
自社で得た成功事例や失敗談、顧客からの導入事例やレビューなどを具体的に盛り込むことで信頼性が増します。 - 専門的な用語やデータを活用(Expertise)
対象ユーザーのレベルに合わせた適切な専門性が求められます。 - 運営者情報の明示(Authoritativeness)
会社概要、執筆者情報、実績などを明記することで信頼性が向上します。 - 正確で更新された情報(Trustworthiness)
情報の鮮度や根拠のある記述が、信頼につながります。
また、キーワードをこれらのE-E-A-T要素と結びつけて構成することで、検索エンジンからの評価が高まりやすくなります。たとえば、「SEO ホームページ キーワード 設定 実例」といったキーワードは、具体性と専門性の両方を含んでおり、上位表示につながりやすい傾向があります。
まとめ
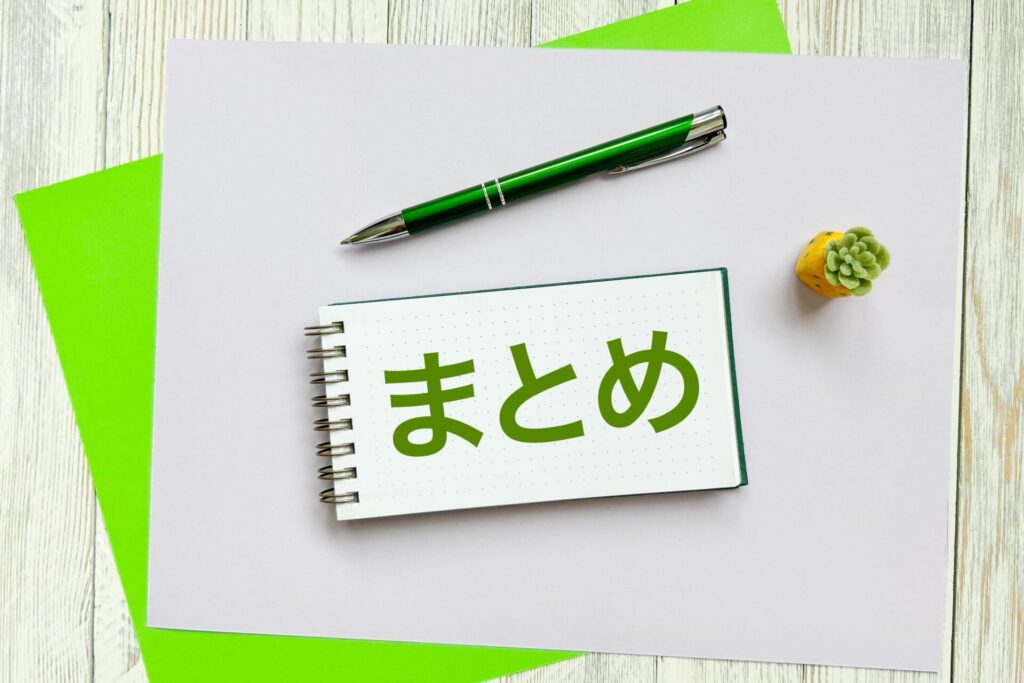
ホームページの検索キーワード設定は、SEO対策の出発点であり、集客や認知向上、そして売上増加に直結する重要な施策です。ただキーワードを詰め込むのではなく、ユーザーの検索意図に寄り添いながら、戦略的に選定・配置・改善を行うことが成果につながります。
この記事では、検索キーワードの基本から、選び方・使い方・失敗事例・改善方法、さらには検索エンジンとユーザーの双方を意識した設計まで、体系的に解説しました。これらを実践することで、SEO初心者でも着実に順位アップとコンバージョン向上が狙えるホームページ運用が可能になります。
助成金を活用したSEO対策・広告運用についてご相談ください
SEO対策を行う上で、最も必要なことは正しい知識を持つことです。外部サービスを利用することも1つの手ですが、IT・DXの推進が加速するこれからの時代、現場で実務を担う人材の育成が不可欠でしょう。
NBCインターナショナルでは、SEO対策やWEB広告運用に関する研修プログラムを用意しています。現役のコンサルタントが講師を務め、eラーニングやZoom研修により、最新の知識と実践力がバランスよく習得できる構成です。
人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで受講費用の約80%が助成対象となります。「SEO対策」や「WEB広告運用のインハウス化支援」といった、集客力アップ・広告運用を内製化するためのサポートを行っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
また、自社でコンテンツを準備する時間が取れない、自分たちで色々試してみたが集客につながらない、そんなお悩みには「SEOコンテンツ制作サービス」もおすすめです。無料でお試しコラムのプレゼントも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

