目次
Webページを設計する際に欠かせないHTMLの見出しタグ。特に「h1」と「h2」は、SEO対策やユーザーの読みやすさに大きな影響を与える要素です。しかし初心者の方やWeb担当者の中には、その違いや正しい使い方がよく分からないまま使っているケースも少なくありません。
この記事では、h1とh2の基本的な役割やSEOにおける意味、実践的な活用方法までをわかりやすく解説します。見出し構造を適切に整えることで、より伝わるコンテンツづくりが実現できます。
h1とh2の役割を理解しよう
HTMLの見出しタグは、Webページの構造を明確にし、情報を整理するために重要な役割を果たします。中でも「h1」と「h2」は、情報の階層構造をユーザーと検索エンジンに正しく伝えるための基本的な要素です。ここでは、それぞれのタグの役割を具体的に理解し、適切に使うための基礎を押さえていきましょう。
見出しタグはWebページの構造を表すHTML要素
見出しタグ(h1~h6)は、HTMLの中でページ内の情報の構造を示すマークアップ要素です。これらは視覚的な装飾を目的とするのではなく、情報の階層性を論理的に表すために使われます。
例えば、書籍における章や節のように、h1が最上位のタイトルを示し、h2がその下位の見出しとして内容を細分化します。こうした構造により、ユーザーはページ内の情報を理解しやすくなり、検索エンジンもコンテンツの主旨を把握しやすくなります。
デザインではなく意味構造としての見出しタグの役割を意識することが、Web制作において重要な基本です。
h1はページ全体の主題を示すタグ
h1は、そのページが何について書かれているかを明示する最上位の見出しです。通常、記事やページのタイトルに使用され、そのページの内容全体を要約する主題を示します。
後程詳しく解説を行いますが、SEO対策の観点から、ページの主題を最も強く示すために、h1タグは1ページに1つだけ使用するという考え方が基本です。検索エンジンもこのタグの内容を重視するため、SEO上も非常に重要なタグとされています。
具体的には、以下のような役割を持ちます。
- ページの中心テーマを表現する
- 検索エンジンにコンテンツの主要トピックを伝える
- ユーザーにとってそのページが何についての情報かを明確にする
h1はコンテンツ設計の起点であり、すべての情報がこの主題に紐づくよう設計されるべきです。
h2はh1の下に位置する小見出しとして使う
h2は、h1で示された主題に対して、その内容を章ごとに分けて説明するための見出しです。構造上はh1の「子要素」にあたり、複数使用することで情報を整理して展開することが可能です。
例えば、「h1=料理レシピ」という主題がある場合、「h2=材料」「h2=作り方」「h2=ポイント」といった形で内容を分けて整理できます。このようにh2を使うことで、ユーザーは情報をセクション単位で把握しやすくなり、ページ全体の可読性が向上します。
また、検索エンジンにとっても、ページ構造が明確になることで適切なインデックスが可能となり、SEOにも良い影響を与えます。
SEOにおけるh1とh2の使い方を正しく理解する

見出しタグは単なるデザイン要素ではなく、検索エンジンにとってもページの構造や主題を把握するための重要な手がかりです。特にh1とh2の使い方は、SEOに直結するポイントでもあります。ここでは、検索エンジンが見出しタグをどう認識し、どのように活用されるのかを正しく理解しておきましょう。
検索エンジンは見出しタグを読み取りページ構造を把握する
Googleなどの検索エンジンは、クローラーと呼ばれるプログラムによってWebページのHTMLを解析しています。その際、見出しタグの構造を参考にして、ページ内の情報を階層的に把握しています。
h1がページ全体の主題、h2がその補足的な内容という構成になっていれば、検索エンジンはそのページがどういう話題について整理されているかを明確に理解できます。逆に、見出しタグが乱雑に配置されていると、クローラーがページ内容を正確に評価できず、SEOの効果が薄れる原因となることがあります。
正しい階層構造を保つことで、検索エンジンにとってもユーザーにとっても分かりやすいページが実現します。
キーワードの適切な配置がSEOに影響を与える
h1やh2タグには、検索されやすいキーワードを自然に盛り込むことがSEO効果を高める基本とされています。ただし、過度に詰め込みすぎると不自然になり、逆に評価が下がるリスクもあるため注意が必要です。
例えば、h1にはそのページ全体の狙いとなるキーワードを1回使用し、h2にはセクションごとのトピックや関連語句を含めることで、検索クエリへの対応力が高まります。このような構成は、ユーザーの検索意図に合致しやすくなり、結果的に検索順位の向上につながります。
キーワードの自然な挿入と、見出しとの意味的な整合性を意識することが大切です。
複数のh1タグを使うことの是非と現在の考え方
HTML5の仕様では、1ページ内に複数のh1タグを使用することが技術的に許可されています。特に、<article>や<section>といったセクショニング・コンテンツごとに、そのセクションの主題としてh1タグを設けることは、文法的に正しい使い方です。
しかし、実務レベルでは「1ページ1つのh1」が今でも推奨されているケースが多くあります。なぜなら、かつて多くの検索エンジンやCMSが最初のh1タグをそのページの主題とみなす傾向が強く、複数あると評価が曖昧になる可能性があったためです。
現在では検索エンジンの性能も改善され、複数のh1タグがあっても問題なく処理できると言われています。
基本的な運用としては、以下のような考え方がベストです。
- 基本的にh1タグは1ページ1つで考える
- ただし、セクション単位で意味が独立している場合は、必要に応じて複数使用も可
h1の数にこだわるよりも、ユーザーと検索エンジンにとって論理的な構造であるかを重視する姿勢が大切です。
見出しタグの階層構造が可読性とアクセシビリティを高める
見出しタグの正しい使い方は、SEOだけでなくユーザーにとっての読みやすさや情報の把握しやすさ、さらにはアクセシビリティの向上にも貢献します。階層構造が明確なページは、視覚的にも論理的にも整理されており、ユーザーの理解を助けます。ここでは、その具体的な効果と理由について見ていきましょう。
適切な階層で情報を整理するとユーザーの理解が進む
情報を段階的に整理することは、読み手の理解を深めるために極めて効果的です。h1でページの主題を示し、h2で章立て、必要に応じてh3以下で詳細を補足する構成にすることで、読者はどこにどんな情報があるのかをすぐに把握できます。
たとえば、長文のページでも見出しが適切に配置されていれば、必要な情報を素早く見つけられるため、ユーザーの離脱率を下げ、滞在時間を伸ばす効果も期待できます。
さらに、視線の流れを意識した構成にすることで、直感的に理解しやすいページ設計が可能になります。
スクリーンリーダーやクローラーも階層構造を評価している
視覚障害のあるユーザーが利用するスクリーンリーダーは、HTMLの見出しタグを頼りにページの内容を読み上げます。論理的に整理された見出し構造は、こうした支援技術にとっても非常に重要です。
また、検索エンジンのクローラーも同様に、見出しを使ってページの構成を把握しています。意味のない順番やスタイル目的のタグ乱用は、SEO評価を下げる可能性があります。
アクセシビリティとSEOの両方の観点からも、見出しの階層構造は「人にも機械にも優しいWebページ」を作るための基本です。
h2以降の見出しも論理的に配置することで読みやすくなる
h1とh2の役割だけでなく、h3やh4といった下位見出しの使い方にも注意を払う必要があります。h2の下に直接h4を配置する、順序が飛ぶなどの構成ミスは、ページ全体の論理性を損ないます。
見出しの構成で意識すべき点は以下です。
- h2の下にはh3、それ以下には順を追って配置する
- 同じ階層の見出しは意味的にも内容的にも並列になるよう整理する
- デザインではなく、情報の論理構造に基づいてタグを選ぶ
このように階層性を守った見出し設計は、読みやすさと信頼感を高める要素となり、ユーザー体験を向上させます。
CMS使用時におけるタグについての注意点とは?
近年、多くのWebサイトでWordPressなどのCMS(コンテンツマネジメントシステム)が活用されています。こうしたツールでは簡単にページ作成ができますが、見出しタグの構造を自動的に出力する機能も多く、注意を怠ると構造の乱れやSEOの機会損失につながることもあります。ここではCMS利用時におけるh1とh2の使い分けの重要性について解説します。
テーマやプラグインが自動的にh1を出力する場合がある
WordPressなどのCMSでは、多くのテーマが記事タイトルをh1として自動的に出力しています。つまり、編集画面でh1タグを手動で挿入すると、1ページ内にh1が複数存在する可能性があるということです。
結果的に分かりにくい構成になってしまう場合もあるため、CMSの仕様を理解したうえで見出しの設定を行う必要があります。またテーマによっては、タイトルがh2で出力されることもあり、使用するテーマのHTML構造を一度確認することが重要です。
本文中のh2以降の使い方でSEO効果に差が出る
見出しタグの適切な使用は、CMSに限らず、どのプラットフォームでもSEOの基本です。特に本文中のh2・h3の使い方によって、情報の整理度や検索エンジンからの評価が変わる可能性があります。
CMSでは見出しのスタイルが視覚的に分かりやすく設定されていますが、装飾に惑わされずに意味構造を意識して使用することが大切です。情報の重要度や内容に応じて、正しい階層でタグを選ぶことが、読みやすさと検索評価の両立に繋がります。
見出しをデザインだけで判断せず構造を意識することが重要
CMSには、見出しタグを視覚的に見せるための豊富なスタイルが用意されています。しかし、デザイン上の見栄えだけを基準にしてhタグを選んでしまうと、本来のHTML構造が崩れてしまいます。
例えば、文字サイズが大きいという理由だけでh1を繰り返し使ってしまうと、ページの主題が不明確になり、SEOにもマイナスの影響を与えるおそれがあります。見出しのタグはあくまでも情報の階層性を示すための要素であるという基本に立ち返ることが重要です。
初心者が陥りがちな見出しタグのよくあるミスと対策
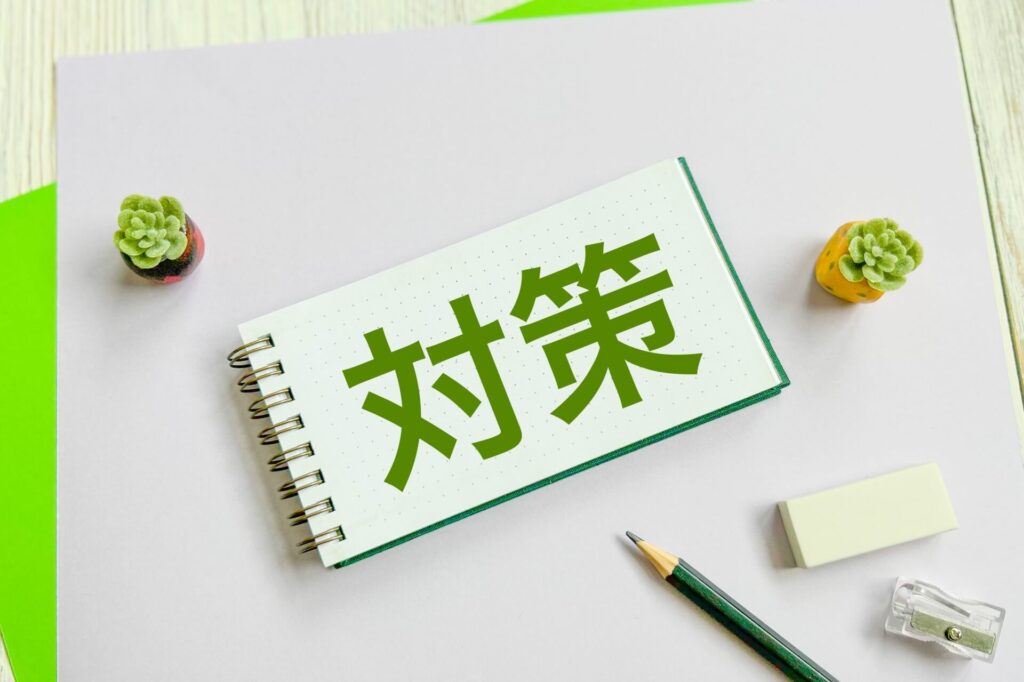
HTMLやCMSに慣れていない初心者の方は、見出しタグの役割や使い方を誤解してしまうことがよくあります。特に、スタイル目的での誤用や論理構造の崩れなどのミスは、可読性やSEOに悪影響を及ぼします。ここでは、よくあるミスとその対策を具体的に解説します。
見出しタグをスタイル目的だけで使ってしまう
初心者がよくやってしまうミスの一つに、「文字を大きく見せたい」「太字にしたい」などの装飾目的で見出しタグを使うというケースがあります。しかし、見出しタグは本来、文書構造を示す意味を持ったHTML要素です。
装飾目的で使ってしまうと、ページ全体の構造が崩れてしまい、SEOやアクセシビリティの観点でもマイナスになります。装飾をしたいだけなら、CSSでクラスやスタイルを設定する方法が適切です。
見出しタグは、「何についてのセクションか」を示すために使うべきであり、見た目で選ぶのではなく、意味に基づいて使うことが原則です。
見出しの順番が飛んでいて論理構造が崩れている
h2の次に突然h4が登場したり、h3の下にh2を入れてしまうなど、見出しの階層が飛んでしまうミスも非常に多く見られます。こうしたミスは、ページ全体の論理構造を不明確にし、検索エンジンや支援技術にも悪影響を及ぼします。
正しい順番で見出しを使うには、以下のルールを守ることが基本です。
- h1 → h2 → h3 → h4 …と、順に階層を下げる
- h2の下にh4を置く場合は、間にh3があるか確認する
- 同階層内では内容の粒度を揃える
見出しは文章構造の骨組みです。構造の順序を守ることで、情報が伝わりやすくなります。
見出しの内容が具体的でなく、ユーザーに伝わらない
見出しタグ自体は適切に使えていても、その内容が「はじめに」「詳細」のように曖昧な単語だけになっているケースも、初心者がよく行うミスの一つです。これでは、ユーザーはセクションを読む前に内容を予測できず、読み飛ばしてしまうかもしれません。
また、検索エンジンも同様に、そのセクションに何が書かれているのかを正確に理解できません。見出しは、そのセクションの「要約」や「タイトル」としての役割を持っています。内容が具体的であればあるほど、ユーザーと検索エンジンの両方にとって親切な構造になります。
h1とh2の違いを理解したうえでの実践的な書き方のコツ
h1とh2の役割と使い方を理解したら、次に重要なのは実際のコンテンツ設計にどう活かすかです。見出しタグはページ構成の骨格となるため、設計段階から戦略的に考えておくことが必要です。ここでは、初心者でも実践しやすい見出しタグの運用ポイントを紹介します。
コンテンツ設計段階で見出しの構成案を用意する
記事やページを制作する前に、見出し構成をあらかじめ設計することが非常に重要です。これはいわば、文章全体のアウトラインを先に作る作業であり、情報の整理と伝達の効率を高めます。
たとえば、以下のような流れを意識すると良いでしょう。
- h1:ページ全体の主題を一文で明確に
- h2:各セクションのテーマや視点を明確に分ける
- h3:h2の内容をより具体化・詳細化する補足見出し
このような設計ができていれば、読者にとってもわかりやすく、検索エンジンにも評価されやすい構成になります。
h1を利用してそのページの明確な主題を示す
h1はそのページの顔ともいえる存在です。したがって、ページのテーマを的確に表す短く明快な文言を選ぶことが大切です。読み手や検索エンジンに対して、そのページが何を伝えたいのかが即座に伝わるようにしましょう。
また、タイトルと同じ文言をh1に設定するのが一般的ですが、状況に応じてタイトルとは異なる表現で具体性を持たせるのも一つの手法です。ただし、どちらの場合でもキーワードは自然に含めるように意識します。
h2以下は論理展開に沿って段階的に配置する
見出しの階層は情報の論理展開を示すものです。h2を使ってページ内のセクションを分け、それぞれがh1の主題に対してどう関係するかを明確にします。さらに、h3はh2を補足・具体化する役割として使い、段階的に情報を深掘りしていくよう構成しましょう。
このような配置を意識することで、読み手にとってストレスの少ないナビゲーションが可能になり、ページ全体の説得力も増します。論理的な見出しの展開は、情報設計の基本として身につけておくべきスキルです。
まとめ
h1とh2の違いを理解することは、Web制作の基本であり、SEO対策やユーザー体験の向上にも直結します。h1はページ全体の主題を示す最も重要な見出しであり、h2はその下位に位置する小見出しとして、情報を分かりやすく整理する役割を果たします。
また、見出しタグはHTMLの意味構造を示すものであり、デザイン目的で使うのではなく論理的な構成に基づいて設定することが重要です。WordPressなどのCMSを使う場合でも、テーマやプラグインの出力構造を理解し、h1とh2を正しく使い分ける意識が求められます。
さらに、見出し構造を事前に設計し、順序や階層を守って段階的に情報を展開することで、検索エンジンにもユーザーにも評価されるページを作ることができます。正しい見出しタグの活用が、コンテンツの価値を最大限に高める鍵となるでしょう。

