目次
Google広告を活用するうえで、広告の効果測定やユーザー行動の分析に欠かせないのがパラメータの設定です。しかし、広告運用初心者や中小企業のWeb担当者の中には、パラメータの役割や設定方法がよく分からず、正確なデータ取得に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、Google広告でのパラメータの必要性から、基本用語の解説、設定方法、外部ツールとの連携方法、さらに実務でありがちなミスとその防止策までを丁寧に解説します。基礎からしっかり学び、計測精度の高い広告運用を実現するための一歩を踏み出しましょう。
Google広告でパラメータが必要とされる理由
Google広告の成果を正しく把握し、運用改善に活かすためには、URLパラメータの活用が欠かせません。特に外部ツールでの効果測定や、より精緻なユーザー行動の可視化を行いたい場合、パラメータは必須の設定項目です。ここでは、なぜGoogle広告にパラメータが必要とされるのか、その背景と目的を解説します。
広告効果をGoogle広告外のツールで測定したい場合
Google広告は独自のコンバージョン計測機能を提供していますが、Googleアナリティクス4(GA4)や他のBIツールを併用して分析する場合は、URLパラメータによるトラッキングが不可欠です。広告経由のアクセスを他のチャネルと明確に区別し、流入元・キャンペーン・キーワードなどの情報を取得するには、パラメータが情報の橋渡し役となります。
特に、広告の成果をサイト全体の動線や他施策との比較で評価するには、Google広告外での一貫したデータ収集が求められます。そのためにも、UTMパラメータなどの設定を正しく行うことが重要です。
トラッキング設定が不十分だと起きるデータ欠損
パラメータの設定ミスや未設定は、広告の効果測定に重大な影響を及ぼします。正しいデータが取得できなければ、どの広告施策が成果につながっているかを判断することができず、運用の方向性そのものが誤ってしまう可能性があります。
特に、以下のような問題が発生しやすくなります。
- 設定漏れや誤った記述により、広告流入が「参照元不明」または「ダイレクト」として計測される
- 流入元が不明確になることで、Google広告の効果を正しく評価できず、予算配分が非効率になる
- サイト内のリダイレクトなどが原因で、パラメータ情報が欠落することもある
これらの問題を防ぐには、URL構成とトラッキングの仕組みを理解したうえで、正確なパラメータ設定を行うことが不可欠です。設定後は、実際の計測結果を検証し、想定通りにデータが反映されているかを確認する習慣も重要です。
パラメータを使った詳細なユーザー行動の可視化
パラメータを活用することで、ユーザーがどの広告をクリックし、どのページを経由して、どのような行動を取ったのかという一連の流れを可視化できます。特に複数の広告バリエーションを運用している場合、それぞれの成果を比較分析するには、精度の高いデータ収集が求められます。
たとえば、「訴求A」と「訴求B」でそれぞれ異なるUTMパラメータを設定すれば、どのクリエイティブがコンバージョンにつながりやすいかを明確に把握できます。こうした詳細なデータは、今後の施策設計において非常に価値あるインサイトをもたらします。
パラメータ設定に関連する主要用語の理解
Google広告でのURLパラメータ運用を正しく行うには、設定に関わる用語や仕組みをきちんと理解しておくことが不可欠です。特に、自動タグ設定やトラッキングテンプレート、ValueTrackパラメータなどは、広告ごとのパラメータ制御に深く関わります。ここでは、パラメータ設定に必要な代表的な用語を分かりやすく解説します。
URLパラメータと自動タグ設定の違い
URLパラメータと自動タグ設定は、いずれも広告の成果を正しく測定するための手段ですが、その仕組みや用途には明確な違いがあります。目的や使用する分析ツールによって、適切な選択が求められます。
まず、URLパラメータとは、リンク先のURL末尾に追加される文字列であり、流入元や広告の詳細情報を計測ツールに伝えるために使用されます。代表的なパラメータとしては「utm_source」「utm_medium」「utm_campaign」などがあり、GA4との連携時によく使われています。
一方、自動タグ設定(Auto-tagging)は、Google広告が自動的に「gclid」というパラメータを付与する仕組みです。これはGoogle広告とGA4間の連携を簡素化するために便利な方法ですが、Google以外のツールではこのgclidを正確に解析できないことがあります。
両者の使い分けは以下のとおりです。
- URLパラメータ(utmなど):外部ツールや手動でのトラッキングに最適。情報のカスタマイズや精緻な分析に向いている。
- 自動タグ設定(gclid):Google広告とGA4の連携に特化。簡単で精度も高いが、Google以外では非対応の可能性がある。
このように、自動タグ設定はGoogle内の連携向け、URLパラメータは外部分析やカスタマイズ重視の用途向けと理解しておくと、適切な計測設計が行いやすくなります。
トラッキングテンプレートと最終ページURLのサフィックスの関係
トラッキングテンプレートとは、URLにパラメータを一括で付与する仕組みです。キャンペーン単位や広告グループ単位などで設定でき、プレースホルダーを用いることで自動的に変数を挿入できます。これにより、広告ごとに異なるURLを手動で作る手間が省けます。
一方、最終ページURLのサフィックスは、リンク先URLの末尾に追加される文字列で、特定のパラメータを指定する際に使います。トラッキングテンプレートと併用することで、柔軟かつミスの少ないURL構成が可能になります。
この2つは連携して動作するものであり、用途に応じてどこで何を設定するかを明確にすることが重要です。
ValueTrackパラメータの基本的な使い方
ValueTrackは、Google広告が提供する動的なパラメータ挿入機能です。{campaignid}や{adgroupid}、{keyword}といったパラメータを使用することで、クリックされた広告の詳細情報をURLに自動的に反映させることができます。
例えば、トラッキングテンプレートに下記のように設定すれば、クリックされた広告のキャンペーンやキーワードの情報をURLに自動で含めることができます。
{lpurl}?campaign={campaignid}&adgroup={adgroupid}&keyword={keyword}
ValueTrackパラメータを活用することで、自社で運用している分析ツールやログ管理システムに、細かな広告情報を正確に渡すことが可能になります。ただし、使いすぎるとURLが煩雑になるため、必要な情報に絞って設定することが肝心です。
Google広告のパラメータ設定方法と適用箇所
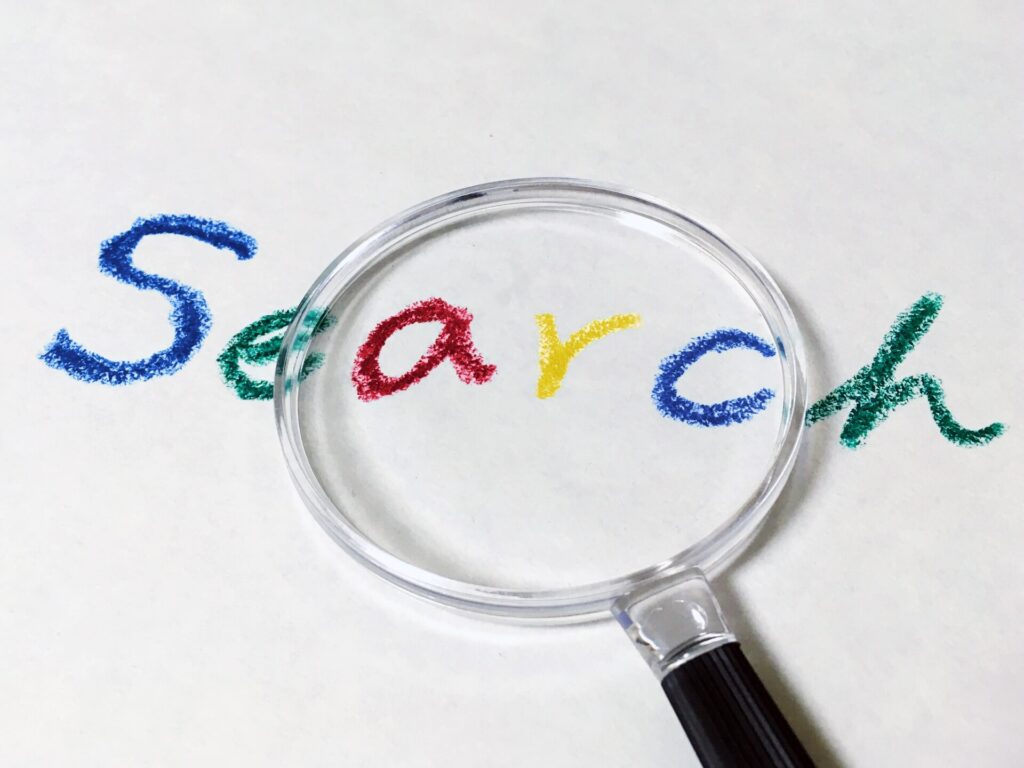
パラメータを正しく設定するには、Google広告のどの階層に、どのように追加するかを理解する必要があります。キャンペーン・広告グループ・キーワード・広告単体など、それぞれに設定できる場所が異なり、目的に応じた使い分けが求められます。ここでは、具体的な設定箇所と方法を解説します。
キャンペーン単位で設定する方法
最もベーシックな設定として、キャンペーン全体に共通のトラッキングテンプレートを適用する方法があります。これにより、そのキャンペーンに属するすべての広告に同じパラメータが反映されるため、管理が簡単になります。
Google広告の管理画面で、キャンペーンを選択し「設定」から「URLオプション」を開き、トラッキングテンプレートを入力することで設定可能です。ここでValueTrackパラメータを用いれば、動的に情報を挿入できます。
例えば、最終ページURLのサフィックスに「source=google」などを設定し、トラッキングテンプレートには「{lpurl}」のみを記述します。この方法は、広告の粒度がそこまで細かくなく、全体の流入状況を把握したいときに有効です。
また、パラメータを設定する際、トラッキングテンプレートに直接 {lpurl}?source=google のように書き込む方法もありますが、この方法は最終ページURLに既に ? が含まれている場合にリンクエラーを起こすリスクがあります。留意しておきましょう。
広告グループやキーワードごとに設定する場合の手順
より詳細な分析を行いたい場合、広告グループ単位、あるいはキーワード単位でパラメータを設定することで、特定の広告訴求や検索語句ごとの成果を明確に可視化できます。
設定方法は、広告グループやキーワードの編集画面から「URLオプション」を選び、トラッキングテンプレートを入力するというものです。ここで設定したテンプレートは、上位階層よりも優先されるため、意図したパラメータが正しく適用されるよう調整が必要です。
この手法は、複数のキーワードや広告グループを比較分析したいときに適しています。
動的検索広告におけるURLの扱いと注意点
動的検索広告(DSA)では、広告文やリンク先URLがGoogleによって自動生成されるため、通常の検索広告と比較してパラメータ設定における注意点が増えます。特に、トラッキングの整合性を保つためには、手動設定と自動生成の関係性を理解し、慎重な運用が求められます。
DSAにおけるパラメータ設定で意識すべき点は以下のとおりです。
- トラッキングテンプレートはキャンペーンや広告グループ単位で設定可能だが、自動生成されるリンク先URLとの整合性を確認する必要がある
- 自動的に挿入される情報との連携には、ValueTrackパラメータを活用し、動的なパラメータ情報を付加する方法が推奨される
- 最終ページURLのサフィックスに手動でパラメータを追加する場合、リダイレクトの挙動やページ表示速度への影響を最小限に抑える構成と事前の検証が重要
このように、DSAの特性を理解したうえで設定を行うことで、トラッキングエラーやデータ欠損を防ぎ、より正確な広告成果の分析が可能になります。
カスタムパラメータとutmパラメータの正しい使い分け
Google広告では、目的や使用ツールに応じて「カスタムパラメータ」と「utmパラメータ」を使い分けることが重要です。それぞれの特徴や用途を理解していないと、トラッキング精度が下がったり、レポートの整合性に影響が出ることもあります。ここでは、両者の違いと具体的な使い方を整理します。
GA4連携にはutmパラメータが不可欠
utmパラメータは、GA4での流入経路を正しく識別するための標準的な手段です。utm_sourceやutm_medium、utm_campaignといったパラメータをURLに付与することで、どの広告や媒体からのアクセスかを明確に記録できます。
Google広告とGA4を自動連携する「gclid」パラメータもありますが、GA4では、自動タグ設定(gclid)を有効にしている場合、手動で設定したutmパラメータよりもgclid経由のデータが優先して使用されます。
utmパラメータがGA4上で反映されるのは、gclidが利用できない場合(例:Google広告以外の媒体)や、意図的に自動タグ設定を無効にしている場合です。
カスタムパラメータで柔軟な情報付与を実現する
カスタムパラメータは、任意の名称と値を設定できる柔軟な仕組みです。Google広告では、{_任意の名前}という形式でテンプレート内に挿入し、それぞれの値を個別に指定できます。たとえば、広告クリエイティブのパターンや担当者名など、標準のタグでは追跡できない情報も追加可能です。
この機能を活用することで、より詳細で実務に即した分析ができるようになり、社内レポートやA/Bテストにも役立ちます。ただし、命名ルールを統一しないと管理が煩雑になるため、社内でのルール作成が不可欠です。
トラッキングテンプレート内での組み合わせ活用例
実務では、utmパラメータとカスタムパラメータ、ValueTrackパラメータを組み合わせて運用するケースが多く見られます。例えば以下のように、パラメータを組み合わせて設定することで、広告単位での精密な分析が可能になります。
例:
{lpurl}?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaignid}&creative={_version}
(※この文字列全体を「トラッキングテンプレート」に設定します)
このような構成により、GA4での流入元分析と、社内分析ツールでのクリエイティブ別評価を同時に実現できます。ただし、パラメータの重複や誤記によってトラッキングが失敗するリスクもあるため、事前の検証とルール設計が重要です。
外部ツールと連携する場合の設定と注意点
Google広告の成果を多角的に評価するために、GA4以外の外部ツールと連携するケースも多く見られます。CRMやBIツール、ヒートマップなど、利用するツールによって必要なパラメータや管理方法が異なるため、連携時にはいくつかの注意点があります。ここでは、設定のポイントとよくある落とし穴について解説します。
GA4以外の計測ツールでの利用を想定したパラメータ運用
外部ツールでは、Googleの「gclid」パラメータが解釈されないことが多いため、カスタムパラメータやUTMパラメータで明示的に情報を付加する必要があります。特に、媒体名・キャンペーン名・キーワードなど、最低限の要素をURL内で明確に渡せるように設定することが重要です。
例えば、BIツールやMA(マーケティングオートメーション)と連携する場合には、「source」「campaign」「medium」などをツールが正しく識別できるよう、事前に仕様を確認しておくべきです。パラメータの互換性を事前に確認せずに連携を進めると、データが欠落する可能性があります。
一貫性を保つための命名ルールと管理方法
複数の広告グループやキャンペーンでパラメータを使い分ける場合、命名ルールの統一が不可欠です。たとえば、「utm_campaign」の値に「promo_2025_summer」といった規則性を持たせることで、分析やフィルタリングがスムーズになります。
命名ルールを曖昧にしたまま運用を開始してしまうと、分析時に「同じキャンペーンなのに別名で記録されている」といった混乱が起きかねません。そのため、スプレッドシートやドキュメントでルールと使用履歴を管理し、チーム内で共有する運用体制を整えることが望まれます。
レポート分析時に確認すべきポイント
パラメータを活用した分析では、設定した値がレポートに正しく反映されているかどうかの確認が極めて重要です。GA4や外部のダッシュボードツールを使って流入経路を確認し、意図通りのデータが記録されていない場合は、何らかの設定ミスや技術的な問題が発生している可能性があります。
特に注意すべきポイントは次のとおりです。
- 設定ミスやリダイレクト処理により、パラメータがURLから消失していることがある
- トラッキング自体は成功していても、パラメータの名称が曖昧だと分析が困難になる
- 数値や記号だけの値ではなく、意味が読み取れる明確な名称を使うことで分析の精度が高まる
こうしたリスクを回避するためにも、導入初期の段階では小規模なテスト配信を実施し、実際にどのようにデータが記録されるのかを事前に確認することが望ましいです。設定内容と計測結果が一致しているかを丁寧にチェックしたうえで、本格的な運用へと移行するのが安全な方法です。
パラメータ運用でよくあるミスとその防止策

URLパラメータは非常に便利な仕組みですが、設定や運用にミスがあると、意図しないデータの欠落や誤認識を引き起こす可能性があります。特に広告チームや複数の担当者で運用している場合、共有不足によるトラブルも少なくありません。ここでは、パラメータ運用でよくあるミスとその防止策を紹介します。
URLが正しくリダイレクトされない問題
パラメータ付きのURLを設定した際に、リダイレクト設定が適切でないと、遷移時にパラメータが消えてしまうというトラブルが発生します。特に、外部LPやサブドメインを利用している場合、リダイレクト処理が広告クリック後にパラメータを失う原因となることがあります。
こうした問題を防ぐには、パラメータ付きURLの動作確認を実施し、リダイレクト後のURLにパラメータが保持されているかをチェックすることが重要です。必要に応じて、Web開発担当者との連携も行いましょう。
パラメータの重複設定によるトラッキングエラー
Google広告では、トラッキングテンプレート、URLサフィックス、最終ページURLの3か所でパラメータを設定できますが、同じパラメータを複数個所に設定してしまうと、URLが重複して壊れたり、計測に失敗することがあります。
たとえば、utm_campaignがテンプレートとサフィックスの両方に記載されていると、意図しないURL構造となるリスクがあります。こうした重複を避けるためには、設定の分担と一元管理を徹底することが防止策となります。
チーム内での共有不足による不整合の発生
パラメータ設定は細かくカスタマイズできる分、担当者ごとにルールが異なるとレポート上で一貫性が失われる原因になります。特に、命名の表記ゆれ(例:「Spring2025」と「spring_2025」)があると、同じキャンペーンなのに別物として認識されてしまいます。
こうした事態を避けるためには、チーム内でのパラメータ命名ルールや設定方針を事前に明文化し、運用開始前に全員で共有する機会を設けることが有効です。また、定期的なレビューとルールの見直しも忘れずに行いましょう。
まとめ
Google広告のパラメータ設定は、広告施策の効果を正確に把握し、改善に活かすための不可欠な仕組みです。URLパラメータやutm、ValueTrack、カスタムパラメータなど、それぞれの形式には役割と使い分けがあります。これらを適切に組み合わせて設定することで、Google広告単体では得られない詳細なユーザー行動や流入経路が見えてきます。
特に、GA4や外部BIツールと連携する際には、パラメータの構造が明確であることがデータの整合性を保つ鍵となります。トラッキングテンプレートの運用や、パラメータの命名ルールも含めたチーム全体での共通認識が、安定した広告分析体制を支えます。
一方で、設定ミスや共有不足は、データの欠落や誤解を招く要因にもなります。リダイレクトや重複の確認、命名ルールの統一といった基本を押さえて運用すれば、こうしたリスクも未然に防ぐことができます。
パラメータ運用は地味で見えにくい作業かもしれませんが、その正確さが広告改善の質を左右します。広告の「打ちっぱなし」ではなく、根拠ある改善を積み重ねるためにも、今一度自社の設定を見直し、確実な計測体制を整えていきましょう。
NBCインターナショナルのデジタル分野の研修/リスキリング支援のご案内
IT・DXの推進には、現場で実務を担う人材の育成が欠かせません。
NBCインターナショナルでは、SEO対策やWEB広告運用に関する研修プログラムを用意しています。現役のコンサルタントが講師を務め、eラーニングやZoom研修により、最新の知識と実践力がバランスよく習得できる構成です。
人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで受講費用の約80%が助成対象となります。
以下に各講座の概要をご紹介します。
Webサイトのデジタル分析技術習得講座
Webサイトの検索順位や成果改善につなげるための、内部対策・サイト解析の実践知識を体系的に習得できる講座です。
検索エンジンの仕組みや構造化データなどの基礎から、GA4やSearch Consoleなどを活用した分析・改善スキルまでを段階的に学べます。
- 内部対策の基礎/応用
- サイト解析と改善実践
- 検索順位低下の原因分析と対応策
習得できるスキル例:
- 検索エンジン最適化の構造的理解
- 内部対策の実践ノウハウ
- 最新のウェブ指標と分析ツール活用法
AIを活用したWEBコンテンツ制作のDX化講座
生成AIツールを活用して、SEOコンテンツ制作を効率化・高度化させるスキルを習得する研修です。
キーワード調査から記事構成、ライティング、アップロードまでを一貫して学び、AIを使ったライティング・リライト手法も実演で体得できます。
- コンテンツSEOの基礎〜実演
- AIツールを用いた制作DX
- キーワード選定やペルソナ設計の手法
習得できるスキル例:
- AIツールによるコンテンツ制作効率化
- ターゲットニーズに応える記事設計
- 実践的なキーワード選定・リライト技術
デジタルマーケティング運用・分析導入による販促DX化講座
広告配信の最適化とデータ分析による販促効果の最大化を目指す企業向け研修です。
リスティング広告・メタ広告の基礎から運用実演、分析による改善手法までを網羅し、広告運用人材の社内育成を目指す企業に最適です。
- リスティング・メタ広告の基礎/応用
- デジタル広告の効果検証と改善実践
- 最新の運用ツールを活用した販促DX
習得できるスキル例:
- 社内での広告運用体制の内製化
- データドリブンな広告改善スキル
- 広告ツールの活用による競争力強化
まずは資料ダウンロード・無料相談からご検討ください
NBCインターナショナルの研修は、SEOや広告運用のノウハウを社内に蓄積し、外注に頼らず自社でマーケティングを改善できる体制づくりを支援する実践型プログラムです。自社の担当者がスキルを習得することで、継続的な集客改善や施策のPDCAを自社内で回せるようになります。
また、人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで、条件を満たせば受講費用の約80%が助成されるため、コストを抑えながら社内人材の育成を進めることも可能です。
資料ダウンロードや無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

