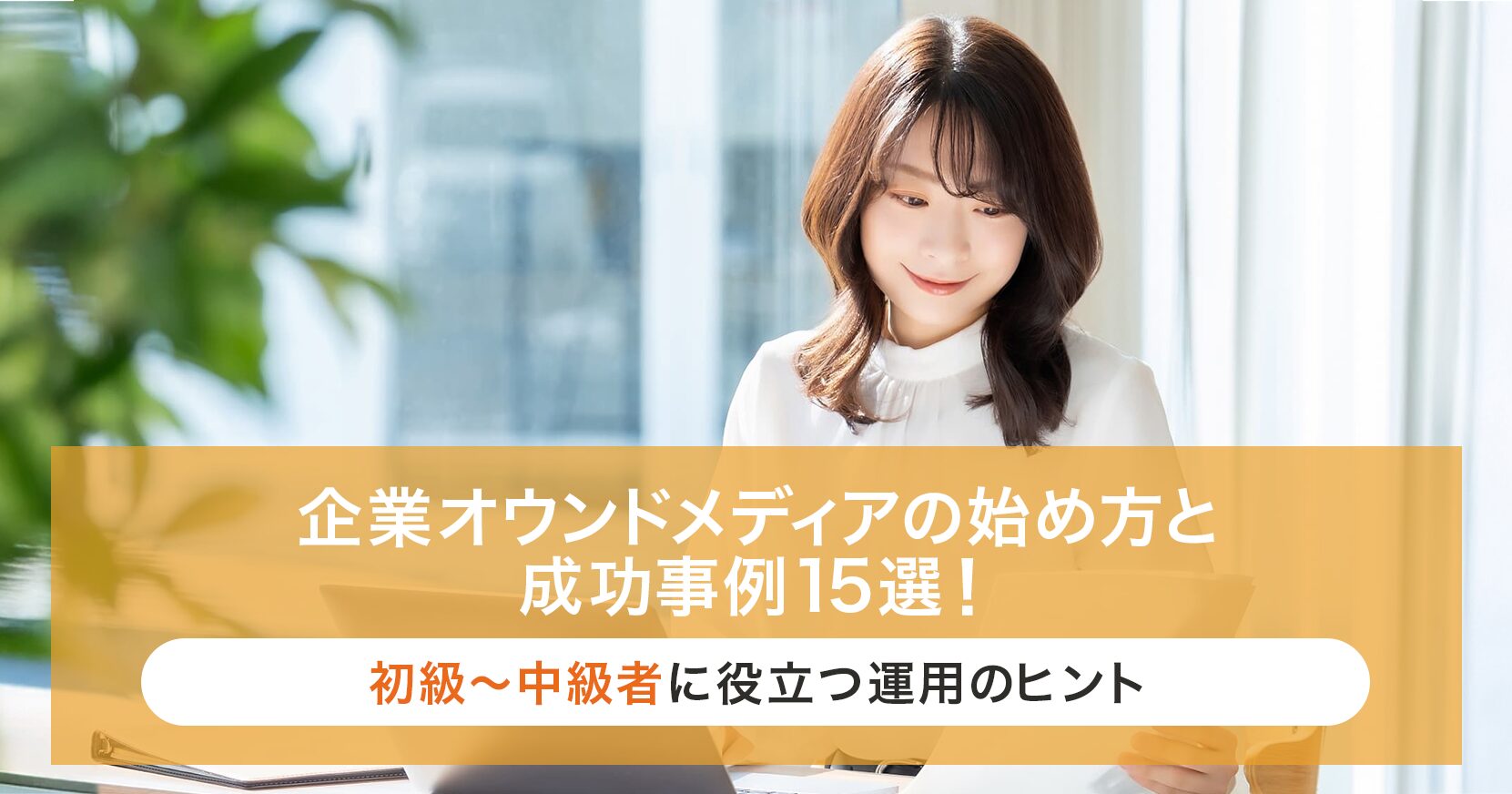目次
企業の広報やマーケティング担当者にとって、自社の魅力やサービス価値を正しく伝える「オウンドメディア」の活用は、重要な選択肢となっています。しかし、立ち上げや運用にあたっては目的の設定やコンセプトづくり、リソースの確保など多くの課題があります。
そこで本記事では、オウンドメディアの基礎知識から、目的別の成功事例、運用のポイントや注意点までを網羅的に紹介します。
読み進めることで、「自社でも実現できる」と前向きに捉えられるヒントや視点が得られる内容となっています。
企業オウンドメディアとは何かを理解しよう
オウンドメディアの運用を成功させるには、まずその基本的な定義や、他の情報発信手段との違いを明確に理解することが欠かせません。
ここでは、オウンドメディアとは何か、企業が保有するメディアの分類、そして情報発信の全体像を整理するPESOモデルをもとに、オウンドメディアの立ち位置を明らかにしていきます。
PESOモデルで見るオウンドメディアの立ち位置
PESOモデルとは、Paid(ペイド)・Earned(アーンド)・Shared(シェアード)・Owned(オウンド)の4つのメディアに分類して、企業の情報発信を整理するフレームワークです。
以下の表でそれぞれの特徴とオウンドメディアの位置づけを確認しましょう。
| メディア種別 | 概要 | 主な媒体 |
|---|---|---|
| Paid(有料) | 広告を通じて露出を得る | リスティング広告、ディスプレイ広告 |
| Earned(信頼) | 他者の評価により拡散される | メディア記事、口コミ、レビュー |
| Shared(共有) | SNSなどでユーザーと双方向の発信 | Twitter、Instagram、YouTube |
| Owned(自社) | 自社が制作・所有・運用する | コーポレートサイト、オウンドブログ |
オウンドメディアとは、自社が直接保有・管理するメディアのことを指します。具体的には、企業のコーポレートサイトやブログ、メールマガジン、会員サイトなどが該当します。
オウンドメディアの特徴は、企業自身の思いや価値を直接伝えられる点にあります。一方で、即効性には欠けるため、長期的な視点で育てていくことが求められます。
企業が保有・運営するメディアの種類
企業が運用できるオウンドメディアには複数の種類があります。それぞれの目的やターゲットに応じて、運用するメディアを選定する必要があります。
主なオウンドメディアの種類
- コーポレートサイト
会社の基本情報やIR情報、ニュースリリースを発信する媒体です。 - サービスサイト・ブランドサイト
商品やサービスの詳細、世界観を伝えるためのメディアです。 - ブログ型メディア
ノウハウや業界情報、事例などを定期的に発信し、SEOにも有効です。 - オウンドSNSアカウント
メディアの一部としてTwitterやInstagramなどのSNSも重要な役割を担います。
目的やターゲットによって、これらを組み合わせて展開することで、効果的な情報発信が実現します。
企業がオウンドメディアを導入する3つの目的

オウンドメディアはただ情報を発信するための媒体ではありません。企業がオウンドメディアを導入する背景には、具体的な目的があります。
ここでは、企業がオウンドメディアを運用する上で代表的な「ブランディング」「採用活動」「リード獲得」の3つの目的に分けて、その狙いや得られる効果について解説します。
ブランディングによる認知・信頼の向上
企業がオウンドメディアを活用する最大の理由の一つがブランディングです。ブランディングとは、商品やサービスだけでなく、企業そのもののイメージを形成・強化する活動を指します。
オウンドメディアを通じて、以下のような内容を継続的に発信することで、読者の認知度を高め、信頼を得ることができます。
- 自社のビジョンや価値観
- 他社にはない技術力や取り組み
- ストーリー性のある実績や事例
特にBtoB業界では、広告や展示会だけでは伝えきれない専門性や独自性を、オウンドメディアで補完するケースが多く見られます。一方的な売り込みではなく、共感や理解を得ることを重視する点がポイントです。
採用活動への活用と応募者との接点づくり
近年、オウンドメディアを採用活動に活用する企業が急増しています。従来の求人サイトや転職エージェントに依存するだけでは、自社に合った人材と出会いにくいという課題があるためです。
採用向けオウンドメディアでは、以下のような情報を発信し、求職者が企業の文化や雰囲気を深く理解する手助けをしています。
- 社員インタビューや職場紹介
- キャリアパスや成長支援制度の紹介
- 働きがいを感じられる取り組みの紹介
これにより、ミスマッチの防止や応募の質の向上が期待できます。
特に中途採用や第二新卒のターゲットに対しては、表面的な条件だけでなく「どんな人が働いているのか」「どんな価値観を大切にしているのか」といった企業の内面を伝えることが重視されます。
見込み客の獲得と営業効率の改善
オウンドメディアはリード(見込み客)獲得のためのチャネルとしても非常に有効です。特にBtoBビジネスでは、比較検討の段階にあるユーザーに向けた情報提供が鍵を握ります。
見込み客の獲得には以下の流れが重要です。
- 検索から自社メディアに訪問(SEO対策されたコンテンツ)
- 課題解決型の記事でユーザーの悩みを解消
- ホワイトペーパーや資料請求でリード情報を取得
- メールマーケティングや営業フォローに接続
このように、営業の前段階でユーザーとの信頼関係を築くことができ、営業活動全体の効率も向上します。
また、定期的に質の高いコンテンツを発信することで、「この会社は業界に詳しい」「この企業の情報は信頼できる」というポジションを築くことが可能になります。
目的別に見る企業オウンドメディアの成功事例15選
企業のオウンドメディアは、その目的によって運用の仕方や発信する内容が大きく異なります。
ここでは「ブランディング」「採用」「リード獲得」の3つの目的に分けて、実際に成果を上げている企業の事例を紹介します。
各企業がどのような工夫をし、どう成果につなげているのかを把握することで、自社の施策に応用できるヒントが得られます。
ブランディングに成功した企業事例
ブランディングを目的としたオウンドメディアでは、企業の思想や文化、専門性を伝えるコンテンツが中心となります。以下に成功事例を紹介します。
1. サイボウズ株式会社「サイボウズ式」
「チームワークあふれる社会を創る」という理念のもと、働き方や組織運営について発信。共感を呼ぶ記事とインタビューでファン層を獲得し、企業イメージ向上につなげています。
2. 株式会社LIG「LIGブログ」
Web制作会社としての専門性を伝えつつ、ユーモアとクリエイティブな切り口で多くの読者を集め、認知拡大とともに採用・集客にも好影響を与えています。
3. note株式会社「note公式マガジン」
自社サービスの活用事例や裏側を発信することで、ユーザーとの距離を縮め、ブランドの信頼性を高めています。
これらの事例に共通するのは、情報発信の軸が明確で、独自の世界観を大切にしていることです。
採用強化に貢献した企業事例
採用活動におけるオウンドメディアの活用は、ミスマッチ防止や応募者の質向上に直結します。
4. クックパッド株式会社「クックパッド開発者ブログ」
エンジニア向けに技術ブログを展開し、社内の開発文化やスキルレベルを公開することで、共感と信頼を集めています。
5. 株式会社ビズリーチ「Reach One」
社員の働き方や制度、インタビューなどを継続的に発信し、リアルな社内の雰囲気を求職者に伝える工夫がされています。
6. 株式会社メルカリ「mercan(メルカン)」
成長企業ならではの変化や挑戦を、ストーリー性あるコンテンツで紹介し、採用ブランディングを強化しています。
採用向けオウンドメディアは、人柄や文化を伝えるコンテンツが鍵となります。
リード獲得に貢献した企業事例
リード獲得を目的としたオウンドメディアは、SEOやコンバージョン設計が非常に重要です。
7. 株式会社ベーシック「ferret」
マーケティング関連のノウハウやツール紹介を継続的に発信し、多数の訪問を獲得。そこからサービスへのリード導入を図っています。
8. 株式会社才流「メソッド/ガイド」
BtoBマーケティングの課題を深掘りし、具体的な改善提案まで掲載。実務者に刺さる情報が豊富で、問い合わせにつながる導線が整っています。
9. 株式会社ユーザベース「Uzabase Journal」
自社サービスの使い方や事例を体系的に紹介し、既存ユーザーの活用促進と新規顧客の関心喚起に成功しています。
10. 株式会社i-plug「人事ZINE」
新卒採用に特化した人事担当者向けメディアとして、採用戦略や学生動向に関する実践的な情報を発信。独自調査に基づくホワイトペーパーの展開により、効果的なリード獲得を実現しています。
11. 株式会社イノーバ「Innovaブログ」
中小企業向けに分かりやすく解説した記事が豊富で、検索流入からのコンバージョン獲得が設計されています。
12. freee株式会社「経営ハッカー」
中小企業向けの業務効率化ツールを紹介する中で、業務課題に直結した記事が、確実にニーズを捉えています。
13. 株式会社ラクス「メールマーケティングラボ」
メール配信サービスの利用促進を目的とし、現場の担当者向けに即効性のある情報を多数掲載しています。
14. 株式会社マネーフォワード「Money Forward Bizpedia」
税務・会計に関する情報提供を通じて、中小企業の実務担当者をサポートしつつ、顧客獲得へとつなげています。
15. 株式会社カオナビ「kaonavi vivivi」
人事担当者向けに、評価制度や組織改革のヒントを紹介し、サービスの理解促進とリード獲得の両立を実現しています。
これらの事例は、ターゲットの課題に応える実践的なコンテンツが鍵になっています。
成功事例に共通する企業オウンドメディア運用のポイント

企業オウンドメディアの成功事例を分析すると、いくつかの共通点が見えてきます。ただ記事を公開するだけでは成果にはつながりません。
ここでは、数多くの企業が実践しているオウンドメディア運用の重要なポイントを紹介します。これらを取り入れることで、安定した成果を目指す土台が整います。
コンセプトとターゲット設定を明確にする
オウンドメディアを運用する上で最初に取り組むべきなのが「コンセプト」と「ターゲット」の明確化です。
これが曖昧だと、どんなコンテンツを発信すべきか、誰に届けるのかが不明確になり、成果に結びつきません。
明確なコンセプト設計のポイント
- 自社ならではの視点や強みを軸にする
- 情報発信を通じて「何を伝えたいのか」を一文で表現する
- 自社とターゲットの交点にあるニーズを把握する
ターゲット設定の注意点
- 年齢や業種だけでなく、「情報収集の方法」「興味関心」「業務課題」などで細分化
- ペルソナを具体化し、その人物に向けて記事を書く意識を持つ
「誰に、何を、なぜ、どう伝えるか」を明文化することで、迷いのないコンテンツ制作が実現します。
ユーザー視点のコンテンツ設計を徹底する
オウンドメディアは、ユーザーにとって価値のある情報を提供する場です。自社の伝えたいことだけを優先すると、読者の関心を引くことはできません。
ユーザー視点を取り入れたコンテンツ設計の方法
- よくある質問や検索キーワードから、読者が抱えている悩みをリサーチ
- 課題に対して「実際に役立つノウハウ」「すぐ使えるテンプレート」などを用意
- 専門用語には丁寧な補足や図解を入れ、読みやすさを意識
特に、検索エンジンからの流入を狙う場合は「SEOと読者満足度のバランス」が不可欠です。専門的な情報であっても、平易な表現と構造化されたレイアウトで提供することが求められます。
KPIとPDCAで継続的に改善する体制をつくる
オウンドメディアは「育てていくメディア」であり、一度作って終わりではありません。成果を出すためには、定期的に数値を確認し、改善を繰り返す運用体制が必要です。
主なKPI指標の例
| 目的 | KPI例 |
|---|---|
| ブランディング | PV数、SNSシェア数、ブランド指名検索数 |
| 採用 | 採用ページ遷移数、応募数、応募の質 |
| リード獲得 | CTAクリック数、資料DL数、フォーム入力完了数 |
PDCAを回すポイント
- 定期的な記事リライトで検索順位やCV率を改善
- 記事公開後のデータを分析して、次の企画に反映
- コンテンツと導線の見直しを常に行う
社内でコンテンツ運用の担当者を育成し、数字と向き合いながら判断する仕組みをつくることが、長期的な成長につながります。
立ち上げ・運用でつまずかないために知っておきたい注意点
オウンドメディアは継続的に運用することで成果を出すメディアですが、その過程で多くの企業が共通の課題に直面します。
ここでは、立ち上げや運用フェーズでありがちなつまずきやすいポイントを3つ取り上げ、事前に対策できるように注意点を整理しておきます。
短期的な成果を求めすぎない
オウンドメディアは長期的な視点で成果を生む仕組みです。
立ち上げから間もない時期に「すぐにリードが取れない」「検索順位が上がらない」と焦ってしまい、運用を中断する企業も少なくありません。
短期的成果を追いすぎることで生じるリスク
- 成果が見えず、関係者のモチベーションが低下
- SEO効果を待たずに施策変更してしまい、効果が出る前に打ち切る
- 一時的な話題性や炎上を狙った、ブランディングに悪影響なコンテンツの発信
立ち上げ半年〜1年は、改善を前提に成果指標を柔軟に設計することが求められます。目先の数字よりも「メディアの型をつくる」「社内に浸透させる」といった中間目標の達成を意識しましょう。
リソース不足への備えと担当者の育成
オウンドメディアが続かない原因として多いのが、運用に必要な人的・時間的リソースの確保不足です。
立ち上げ時は熱量が高くても、日常業務に追われて記事更新が止まってしまうケースは珍しくありません。
リソース確保のためのポイント
- 初期段階から「月に何本更新できるか」を現実的に見積もる
- 外部ライターや編集者の活用も視野に入れる
- 担当者が辞めても引き継げるように運用マニュアルを整備する
また、広報やマーケティング部門が兼任で担当する場合は、社内での知識共有や編集会議を通じて、チームとしてのスキルアップを図ることも重要です。
コンテンツ制作とSEOの両立を意識する
「読者に伝えたいこと」と「検索されるキーワード」は必ずしも一致しません。SEOを意識せずに書いた記事は、どれだけ質が高くても読まれないリスクがあります。
コンテンツ制作とSEOの両立方法
- 検索ボリュームのあるキーワードを調査してから企画を立てる
- タイトルや見出しには自然にキーワードを盛り込む
- 読者にとって有益な内容に加え、内部リンクやメタ情報も整備する
ただし、SEOを優先しすぎて不自然な文体になったり、読者の期待に応えない内容になるのは逆効果です。常に「検索ユーザーの意図」に寄り添う姿勢を持ちましょう。
他社の成功事例を自社の課題解決にどう活かすか

オウンドメディア運用で成果を出すためには、成功事例をただ真似するのではなく、自社の状況に応じて「なぜ成果が出たのか」を読み解く視点と、応用するための戦略が必要です。
ここでは、他社の成功要因の見方、自社に合った活用方法、そして「自社でも実現できる」と前向きに取り組むための考え方を紹介します。
成功要因を目的別に読み解く視点
成功事例を参考にする際には、「どの目的で、何を実践したのか」を分解して分析することが重要です。例えば、同じブログ型オウンドメディアでも、ブランディング目的とリード獲得目的では戦略やコンテンツの内容が異なります。
成功事例を読み解くポイント
- 目的との整合性
例:採用目的なら「社員の顔が見えるコンテンツ」が充実しているか - コンテンツの種類と構成
ノウハウ記事、事例紹介、インタビューなどのバランス - ユーザーとの接点のつくり方
CTA(行動喚起)の設置やSNS連携、フォーム誘導の設計
成果の背景には、ターゲットや業界特性に応じた判断があるため、「なぜうまくいったのか」を自分の言葉で説明できることが活用の第一歩です。
自社リソースに合わせた戦略立案のヒント
他社の成功事例に影響されて、リソースを超えた運用計画を立ててしまうのは失敗の元です。自社の状況に合った戦略立案が、持続可能なメディア運営のカギを握ります。
リソースに応じた計画の立て方
- スモールスタートで開始
月1〜2本の更新でも、戦略性のあるコンテンツなら十分 - 一人チームでもできる運用体制の工夫
テーマを絞った連載型、テンプレート活用、過去記事の再編集など - 外注と内製の使い分け
コアなノウハウは自社制作、SEO記事は外注、と役割を明確にする
「自社にしかできない情報発信は何か」を軸に据え、等身大のリソースでできる範囲から成果につなげる工夫が重要です。
「自社でも実現できる」と考えるために必要な思考法
オウンドメディアは中長期の取り組みであるため、前向きに粘り強く取り組めるマインドセットが欠かせません。
成功事例を見ると「うちは無理」と感じがちですが、視点を変えることで見える可能性は大きく広がります。
前向きに取り組むための思考法
- 「あれもこれも」ではなく「これだけはやる」から始める
- 競合ではなく「過去の自社」と比較して進捗を見る
- 定性的な変化にも目を向ける(社員の反応、採用の質など)
- 関係者との情報共有をこまめに行い、成功体験を可視化する
成功事例を自社の未来像として捉えることで、自分たちにもできる一歩が見えてきます。その積み重ねが、やがて他社から学ばれる側になる道筋になります。
まとめ
企業がオウンドメディアを活用する意義は、単なる情報発信を超えて、自社のブランディング強化、採用活動の促進、リード獲得といった多目的な成果をもたらす点にあります。本記事では、オウンドメディアの基本的な位置づけから、目的別の成功事例、運用のポイント、注意点までを体系的に解説しました。
特に重要なのは、自社に合ったコンセプトとターゲットを明確に定め、ユーザー視点を大切にしながら、数値に基づいた改善を続けていく姿勢です。さらに、他社事例を盲目的に真似るのではなく、自社の課題やリソースに合わせて最適な施策に落とし込む視点を持つことで、「自社でも実現できる」という確信が生まれます。
企業の広報・PR担当者やマーケティング初級者であっても、地に足のついた設計と運用体制を築けば、成果につながるオウンドメディアを持つことは十分可能です。まずはできる範囲から一歩を踏み出し、自社らしいメディアの形をつくり上げていきましょう。