目次
Webサイト運営において、定期的かつ高品質な記事を安定的に供給することは大きな課題です。
とくにSEO対策を意識したコンテンツ制作には専門的な知識と経験が求められるため、外部に記事作成を依頼する企業が増えています。しかし、どの代行サービスを選べばよいのか、どこに注意すべきかを判断するのは容易ではありません。
ここでは、記事作成代行の基礎知識から選び方のポイント、さらにおすすめの10社まで詳しく紹介します。貴社にとって最適なパートナーを選定するための判断材料にお役立てください。
記事作成代行とは
記事作成代行とは、企業や個人が運営するWebメディアやブログに掲載する記事の執筆業務を、外部の代行会社に依頼するサービスです。
ここでは、どのような業務を依頼できるのか、またクラウドソーシングとの違いについて解説します。記事作成を外注化する前に、基本的な仕組みを理解しておくことで、後悔のない選択ができるようになります。
依頼できる業務内容
記事作成代行会社が対応する業務は、単なる「文章執筆」だけにとどまりません。以下のように、コンテンツ制作全体に関わる幅広い業務を請け負ってくれるケースが多くあります。
- キーワード選定
- 記事構成案の作成
- 競合調査や検索意図分析
- SEOを考慮したライティング
- 校正・校閲
- CMSへの入稿やアイキャッチ画像の作成
これらを一括で対応してくれる代行会社を選べば、社内での編集作業をほとんど発生させずに高品質な記事を公開することが可能になります。マーケティングリソースが限られている企業にとっては、非常に大きなメリットとなります。
クラウドソーシングとの違い
クラウドソーシングは、個人のライターに直接業務を依頼する形式が多く、コスト面では安価で済む場合もあります。しかし、品質管理や進行管理を自社で行う必要があるため、運用工数が大きくなる傾向があります。
一方、記事作成代行会社は、専任のディレクターが全体をマネジメントし、ライターや校正者と連携して記事を仕上げる体制が整っています。そのため、社内の負担を減らしつつ、品質と成果の両立が期待できる点が最大の違いです。
目的や運用体制に応じて、どちらが自社に合っているかを見極めることが大切です。記事の品質を重視したい場合や、継続的に大量の記事を制作したい場合は、記事作成代行会社の利用がより適しているといえます。
記事作成代行のメリット・デメリット
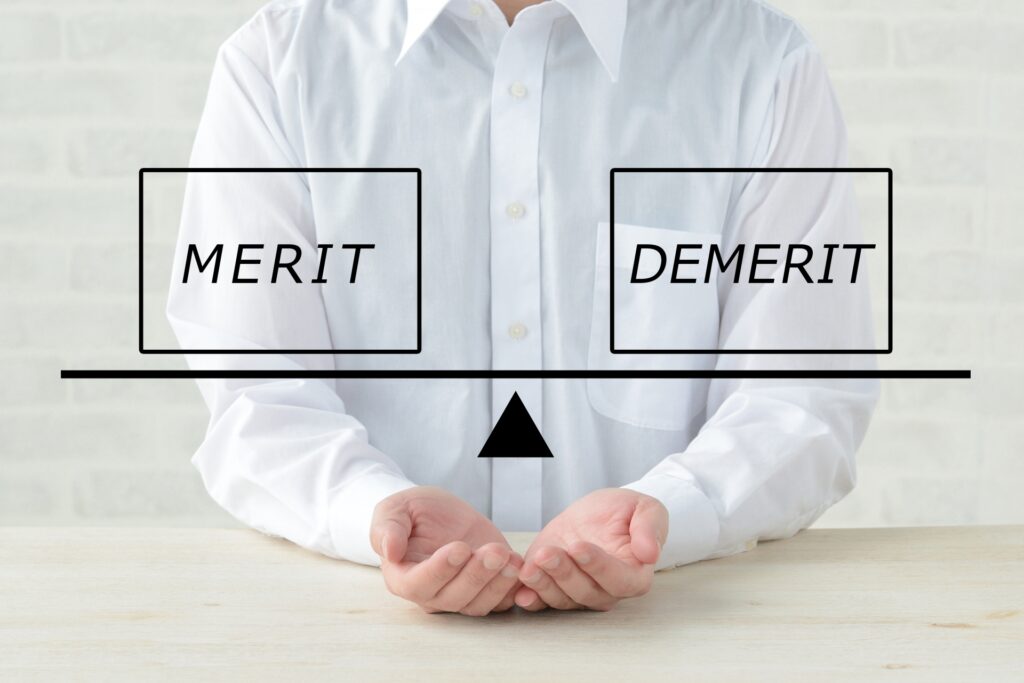
記事作成代行を活用することで、自社のリソースを節約しながら高品質なコンテンツを提供できる可能性が広がります。しかし、導入にあたっては注意すべき点もあります。
ここでは、記事作成代行の代表的なメリットとデメリットをそれぞれ解説し、外注を成功させるために知っておくべき基本を整理します。
工数削減や専門知識の活用ができる
記事作成代行を活用する最大の利点は、社内の作業負担を大幅に軽減できる点にあります。特に、オウンドメディアを持つ企業にとって、継続的なコンテンツ発信は時間と労力を要します。
記事作成代行では、以下のような作業を任せることができます。
- SEOに基づくキーワード調査と戦略立案
- 読者ニーズを踏まえた構成とライティング
- 複数人による校正・編集体制の構築
これにより、プロの視点で精度の高いコンテンツ制作が可能になり、社内では企画やチェックなど本質的な業務に集中できます。
特に、専門性の高いテーマを扱う場合、ライターの知見を活用することで、ユーザー満足度の高い記事を提供できるようになります。
品質やコスト面の注意が必要
一方で、記事作成代行にはいくつかのデメリットも存在します。とくに注意したいのは、品質とコストのバランスです。安価なサービスに飛びつくと、次のようなリスクが生じます。
- ライターのレベルが低く、内容の薄い記事になる
- コミュニケーション不足により、意図と異なる記事が納品される
- 修正対応に時間がかかることで、納期が遅れる
また、発注前に業務範囲を明確にしておかないと、追加費用が発生する場合もあります。初めて依頼する場合は、テスト記事の実施や、ディレクターのサポート体制があるかをチェックすると安心です。
品質を重視するのであれば、ある程度の費用は必要です。そのため、コストだけで判断せず、実績や制作フローも含めて総合的に比較検討することが重要です。
記事作成代行の料金相場
記事作成代行を検討する際、多くの方が気になるのが料金体系です。サービスによって料金形態や相場は異なるため、予算や目的に合わせた選定が必要です。
ここでは、一般的な料金形態の違いと費用感について詳しく解説します。コストに対する不安や疑問を解消し、納得のいく外注ができるようサポートします。
文字単価・記事単価・月額固定の違い
記事作成代行には、主に以下の3つの料金体系が存在します。それぞれの仕組みを理解することで、自社に合った契約方式を選びやすくなります。
- 文字単価型
文字数に応じて料金が決まる方式です。1文字あたり2円〜10円程度が一般的で、文字数の多い記事ではコストが増加します。ライターへの直接依頼やクラウドソーシングでよく見られます。 - 記事単価型
1記事ごとに定額で料金が設定されている方式です。料金が明確で見積もりが立てやすい反面、記事のボリュームが少なくても高く感じることがあります。 - 月額固定型
月に数本の記事制作をセットにして提供する方式です。継続的に記事を依頼する企業にはコストパフォーマンスが良く、専任ディレクターがつくケースも多いのが特徴です。
自社のコンテンツ発信の頻度や運営体制に合わせて、適した料金形態を選ぶことが成功の鍵となります。
費用相場
記事作成代行の費用相場は、依頼内容や品質によって大きく変わります。以下の表に、代表的な費用相場をまとめました。
| サービス内容 | 相場価格(税抜) | 特徴 |
| 個人ライター(実績少) | 1.5円〜3円/文字 | 安価だが品質管理やディレクションは自社対応が必須 |
| 専門ライター(SEO対応) | 5円〜15円/文字 | 専門分野やSEOの知見があり高品質だが、単価は高め |
| 記事単体の受注(構成+執筆) | 15,000円〜50,000円/1記事(3,000~5,000字程度) | SEOや校正込みで、一定の品質が期待できる |
| 月額契約(10記事以上) | 100,000円〜500,000円/月 | 安定供給とディレクション付きで、運用負荷を軽減できる |
安価なサービスは魅力的に見えますが、品質や成果が伴わないと結果的に損失となる場合があります。SEOに強い記事を希望する場合や、継続的に運用したい場合は、ある程度の予算確保が必要です。
費用だけでなく、内容・対応体制・実績も含めて総合的に判断することが、満足度の高い依頼につながります。
記事代行業者を選ぶ5つのポイント
数多く存在する記事作成代行会社の中から、自社に最適なパートナーを選ぶには、いくつかの重要な視点を押さえる必要があります。
ここでは、選定時に注目すべき5つのポイントを解説します。信頼できる代行会社を見極め、失敗のない外注を実現するための判断基準を身につけましょう。
ライターのスキル・実績
記事の品質を大きく左右するのが、執筆を担当するライターのスキルと実績です。専門知識の有無、SEOへの理解度、構成力や表現力などを確認することが大切です。
以下の点をチェックするとよいでしょう。
- 専門分野に強いライターが在籍しているか
- 過去の執筆実績やサンプル記事があるか
- 編集者や校正担当者によるチェック体制があるか
表面的な安さに惑わされず、実力あるライターが揃っているかどうかを見極めることが成功の鍵です。
対応ジャンルとSEOの知見
すべての代行会社が、あらゆる業界に対応しているわけではありません。自社の業種・ジャンルに精通しているかを確認することが大切です。
また、SEOに強い代行会社であれば、以下のような支援が期待できます。
- 適切なキーワード選定
- 内部リンクや見出し構造の最適化
- 検索意図を捉えた記事構成
SEOの知見があるか否かは、集客効果を大きく左右する要因です。対応分野とSEOノウハウを併せ持つ代行会社が理想です。
専任ディレクターの有無
代行会社によっては、ディレクターが付き、全体の進行管理や品質チェック、ライターとの橋渡しを行ってくれます。特に多忙な担当者にとっては、非常にありがたい存在です。
ディレクターがいることで期待できるメリットは以下の通りです。
- ヒアリングを通じたコンテンツ設計
- 品質管理とフィードバック体制の強化
- スケジュールの調整と納期遵守
プロジェクト全体を安心して任せられるかどうかは、ディレクターの有無に大きく左右されます。
実績・事例の確認
選定前には、必ず代行会社のこれまでの実績や事例を確認しましょう。実際にどのような成果を出しているかを見ることで、信頼性や適性が判断できます。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- どの業界のコンテンツを制作した実績があるか
- 検索順位やPV数など、成果の指標を提示しているか
- 公開されている導入事例やクライアントの声があるか
具体的な実績があるほど、その代行会社の信頼性は高まります。
修正対応や連絡体制
納品後に「思っていた内容と違う」ということが発生しないように、修正対応の有無や範囲を事前に確認しておくことが重要です。
また、円滑なやり取りを実現するためには、連絡体制も要チェックです。
- 修正依頼は何回まで可能か
- どのような方法でやり取りを行うか(チャット、メールなど)
- 回答までのスピードや対応姿勢
柔軟で迅速な対応ができる代行会社ほど、長期的な信頼関係を築きやすくなります。初回相談時からの対応も含めて、総合的に判断しましょう。
おすすめ記事作成代行10社の比較
記事作成代行を選ぶとき、実績・得意分野・品質などそれぞれ異なる特長があります。
ここでは、目的やニーズに応じて選べる10社を3つのカテゴリーに分けてご紹介します。ご自身の優先順位に応じて選定される際の参考にしてください。
Webメディア支援に強い会社
ここでは、特に豊富なメディア運営支援の実績を持つ企業を紹介します。
サムライト株式会社
大手メディアや自社メディアの運営支援を多く手がけています。構成案の制作から校正までワンストップで提供されるため、手間をかけずに記事制作を依頼したい企業に適しています。
テクロ株式会社
専門ジャンルごとのライターネットワークが強みです。業界に特化した記事制作に強く、SEO対策も得意です。特にテクノロジーやビジネス系のコンテンツで実績があります。
株式会社アナザーパス
専任ディレクター制を導入し、クライアントとの連携を重視しています。品質管理に強みがあり、中堅メディアの運営サポートに適しています。
NBCインターナショナル株式会社
無料でお試しコラムのプレゼントを行っているため、まずは見てみたい、という場合におすすめです。幅広いジャンルのコンテンツに対応しています。
SEO特化型の会社
検索エンジン上位表示に注力したサービスを提供している企業を紹介します。
株式会社ウィルゲート
SEOコンサルから記事制作まで一貫したサービスを提供しています。データドリブンなキーワード選定と内部施策の提案が強みです。
株式会社ニュートラルワークス
自社CMSと連携した記事運用が可能で、サイト構造を踏まえたSEO対応に定評があります。技術系や専門性の高いテーマへの強みがあります。
株式会社SEデザイン
美容・健康分野に加え、BtoBマーケティングやIT領域など、幅広いジャンルで検索意図を重視したコンテンツ制作に強みを持っています。特に美容・健康・ライフスタイルといったジャンルでの実績があります。
株式会社EXIDEA
月額定額プランでの記事提供と、継続LPO/SEO改善支援が魅力です。継続的にサイト改善したいメディアにおすすめです。
コスパ重視の会社
限られた予算で品質も求める企業におすすめのサービスです。
シュワット株式会社(記事作成代行ウルトラ)
低価格ながら文字単価・記事単価形式が選択可能で、予算に応じたプラン選択が可能です。品質担保の校正体制付きなのもポイントです。
株式会社BRIDGEA(記事作成代行Pro)
月額固定プランがあり、専任担当者のサポート付きで安定した運用ができます。初めて記事代行を導入する企業に適しています。
外注で失敗しないためのポイント
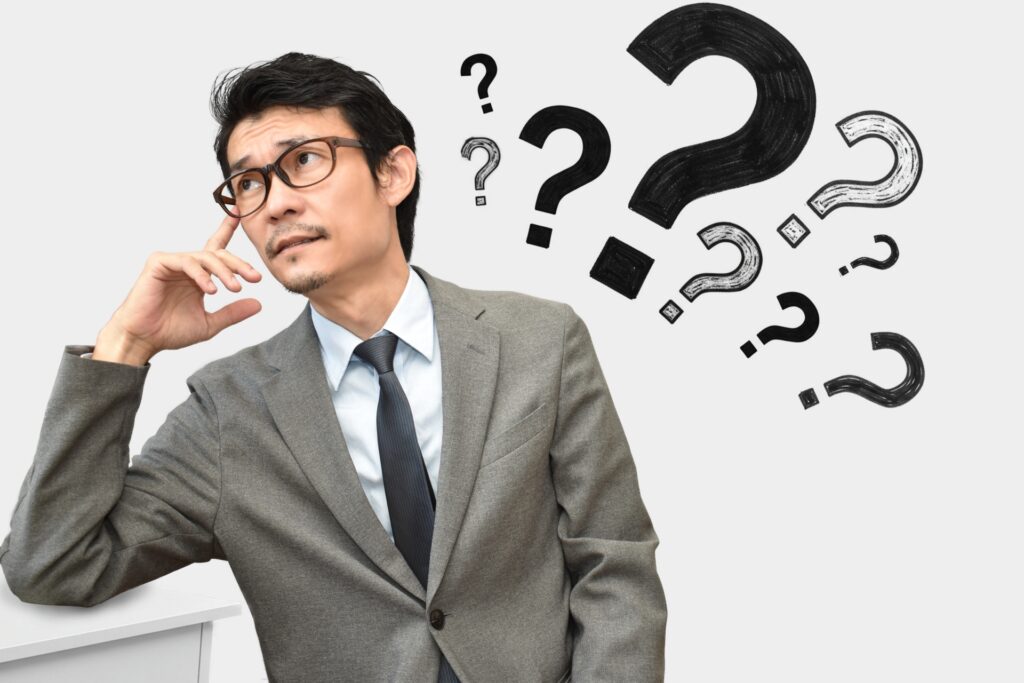
記事作成代行の外注は、運用の効率化や成果向上につながる一方で、進め方を誤ると期待通りの効果が得られない可能性もあります。
ここでは、外注で後悔しないために事前に押さえておきたいポイントを紹介します。信頼できるパートナーを見極めるためにも、実践的な注意点を確認しておきましょう。
目的と方針を明確にしておく
まず重要なのは、記事作成を外注する目的と方針を明確にすることです。目的が曖昧なまま依頼を始めてしまうと、納品された記事の方向性がズレてしまうリスクがあります。
以下のような点を事前に整理しておくと良いでしょう。
- コンテンツのターゲット読者
- メディアのゴール(集客、ブランディング、CV獲得など)
- 記事のトーンや雰囲気
- SEOキーワードの選定方針
発注側の意図をしっかり伝えることが、質の高いコンテンツに直結します。要件定義がしっかりしているほど、満足度の高い納品が得られやすくなります。
継続支援や対応範囲も含めて会社を選ぶ
単発での依頼ではなく、中長期的に付き合えるパートナーかどうかも重視すべきポイントです。特にオウンドメディアを成長させるには、継続的な改善と運用が欠かせません。
- 毎月の進捗報告や改善提案があるか
- コンテンツの分析・改善もサポートしてくれるか
- 記事の制作以外(画像制作、SNS連携など)も依頼できるか
このような点を確認することで、単なる外注先ではなく、運用パートナーとして信頼できる企業を選びやすくなります。
テスト記事とヒアリングで相性を確認する
実際の依頼前に、テスト記事を作成してもらうことで相性を見極めることが可能です。記事の品質だけでなく、やり取りのスムーズさや対応の丁寧さなど、細かな部分も評価対象となります。
また、事前ヒアリングが丁寧かどうかも重要です。
- ヒアリングの深さや質問内容の的確さ
- こちらの要望を汲み取る姿勢があるか
- 提案力があるかどうか
一度テストを通して、実際の仕事ぶりを体験しておくことが、失敗のリスクを減らすために非常に効果的です。外注先との信頼関係を築く第一歩として活用しましょう。
まとめ
記事作成代行を活用することで、専門知識や工数の不足を補いながら、高品質なコンテンツを効率的に発信できます。
クラウドソーシングとの違いや、依頼できる業務内容を理解した上で、自社に合った料金体系や対応ジャンル、SEOの知見を持つ代行会社を選定することが成功の鍵です。
とくに重要なのは、目的を明確にし、ディレクションや修正対応までしっかり対応してくれるパートナーを選ぶことです。
記事作成代行の活用によって、Web集客やオウンドメディア運営の成果が最大化されるよう、この記事で紹介した内容をぜひ参考にしてみてください。
助成金を活用したSEO対策・広告運用についてご相談ください
SEO対策を行う上で、最も必要なことは正しい知識を持つことです。外部サービスを利用することも1つの手ですが、IT・DXの推進が加速するこれからの時代、現場で実務を担う人材の育成が不可欠でしょう。
NBCインターナショナルでは、SEO対策やWEB広告運用に関する研修プログラムを用意しています。現役のコンサルタントが講師を務め、eラーニングやZoom研修により、最新の知識と実践力がバランスよく習得できる構成です。
人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで受講費用の約80%が助成対象となります。「SEO対策」や「WEB広告運用のインハウス化支援」といった、集客力アップ・広告運用を内製化するためのサポートを行っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
また、自社でコンテンツを準備する時間が取れない、自分たちで色々試してみたが集客につながらない、そんなお悩みには「SEOコンテンツ制作サービス」もおすすめです。無料でお試しコラムのプレゼントも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

