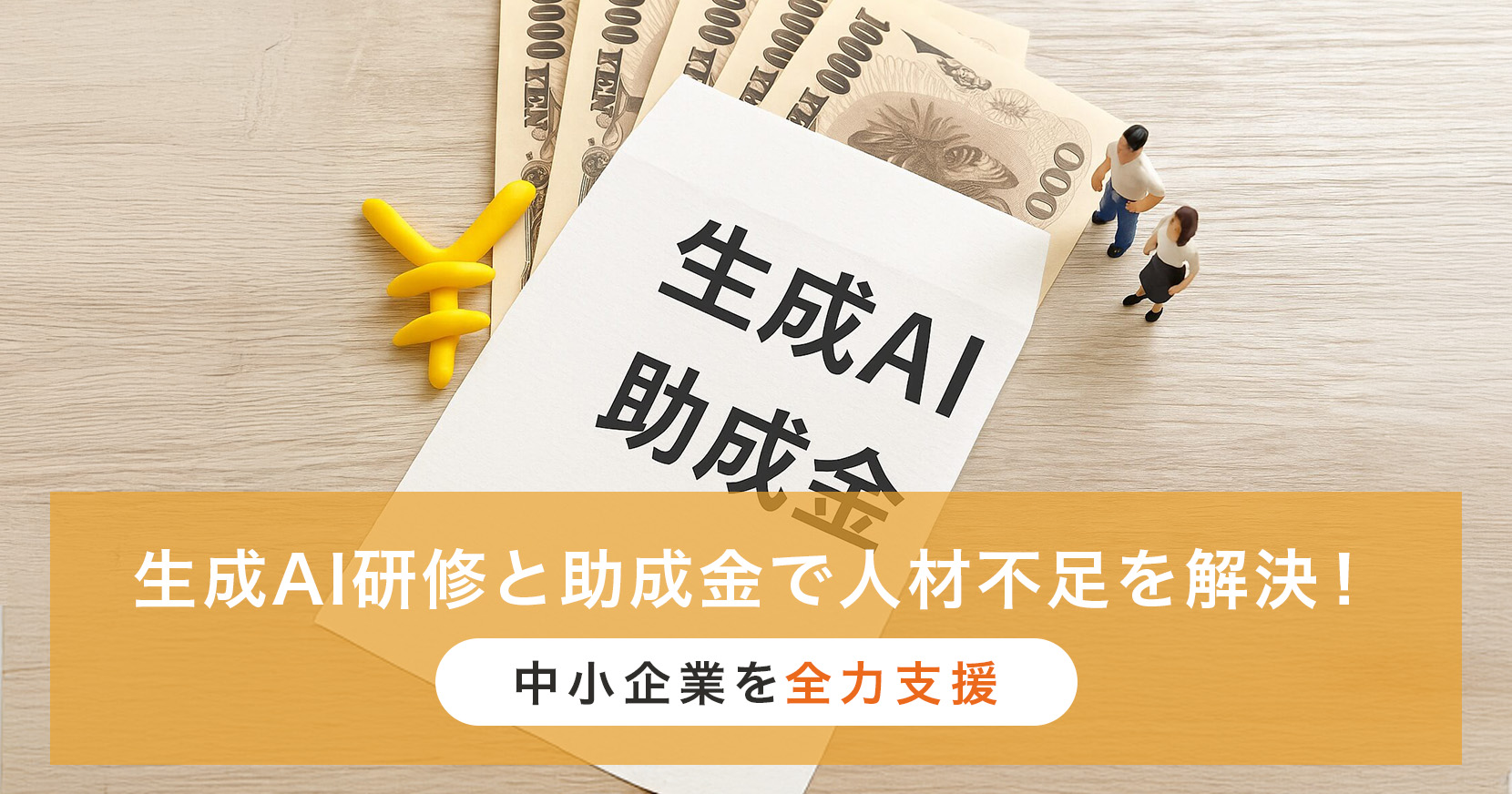目次
生成AIの活用が進む現代、業務効率化や競争力強化のためにAI人材の育成が急務となっています。しかし中小企業では、コストやノウハウ不足が大きな壁となって導入をためらうケースが少なくありません。
ここでは、助成金を活用して費用負担を抑えつつ、生成AI研修を導入する方法を詳しく解説します。助成対象となる具体的な制度から申請手続き、よくある落とし穴まで網羅し、導入準備をスムーズに進められる内容となっています。
コストを抑えてAI人材を育てる具体的なステップを把握し、自社のDX推進に大きく前進できる情報をお届けします。
生成AI研修とは?中小企業が導入すべき理由とメリット
生成AIは、文書作成や画像生成、情報整理など、従来は人が行っていた知的業務の多くを自動化できる革新的な技術です。特に中小企業においては、人手不足や業務の属人化といった課題の解決策として、生成AIの活用は有効となる可能性が高く、AI研修の導入は経営力を高める大きなチャンスとなります。
ここでは、生成AI研修によってどのような人材が育つのか、なぜ今このタイミングでAI活用に踏み出すべきなのかを解説します。
生成AI研修で育つ人材と業務改善の可能性
生成AI研修を受けた社員は、AIツールを使いこなすだけでなく、「業務にどのようにAIを取り入れるか」を自ら考え、実行できる能力が身につくことも期待できます。これは単なるツール操作とは異なり、AI導入による業務改善の設計や効果測定、改善提案ができる実践的なスキルです。
また、次のような業務で効果が期待できます。
- 定型資料や報告書の作成時間を大幅短縮
- マーケティング資料の効率的な作成
- 顧客対応文書やFAQの自動化による業務負荷軽減
生成AIのスキルを持った社員は、企業のDX推進の中心となり得る存在です。中小企業こそ、柔軟な組織体制を活かしてAI活用を先行する好機です。
AI活用に関心がある企業が「今」動くべき背景
生成AIの技術は急速に進化しており、今後数年のうちに企業競争力に直結するスキルになると予測されています。早期に研修を導入し、社内にAIリテラシーを持つ人材を育成しておくことで、他社との差別化が図れます。
また、国や自治体が「人材開発支援助成金」などの制度を通じて積極的に支援している今こそが、コストを抑えてAI研修を導入する絶好のタイミングです。助成金は予算が限られ、期間限定の制度もあるため、早めの行動が有利です。
このように、中小企業が生成AI研修を導入することで、人材育成と業務効率化を両立し、持続的な成長戦略を描くことが可能となります。
生成AI研修で活用できる助成金制度一覧と特徴

生成AI研修は費用がかかる一方で、多くの中小企業にとって業務改善の大きな可能性を秘めています。こうした研修費用を軽減できる手段として、厚生労働省や自治体が提供する複数の助成金制度が存在します。
ここでは、代表的な助成金制度の特徴と、生成AI研修にどのように適用できるかを分かりやすく解説します。
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、生成AIなどの先進技術を活用し、新たな業務領域に必要なスキルを習得する研修を対象とする助成制度です。
特に、DXや業務改善に直結する実践的な内容であれば、助成対象となる可能性が高い制度として注目されています。
【主なポイント】
- OFF-JT(職場外研修)が対象
- 研修費用の経費助成(中小企業は75%、大企業は60%)
- 受講者1人あたり賃金助成(中小企業:1時間960円/大企業:480円)
生成AIツールの基本操作のみではなく、業務効率化や業務設計の改善につながる活用方法までカバーした研修であることが、助成対象として認められる重要な条件となります。
そのため、「ChatGPTの使い方を学ぶ」だけでなく、社内でどのようにAIを活用して業務を再構築できるかを含んだカリキュラム設計が求められます。
人材育成支援コース・教育訓練休暇等付与コース
人材開発支援助成金の中でも「人材育成支援コース」や「教育訓練休暇等付与コース」も、生成AI研修との相性が良い制度です。
【違いとポイント】
| コース名 | 特徴 | 対象となる可能性があるケース |
|---|---|---|
| 人材育成支援コース | 中長期的な社員育成計画に基づく研修に対応 | 計画的にAI人材を育てたい場合 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 従業員の自己啓発支援を促す仕組みを整えた企業向け | 自主的にAIを学ぶ社員を支援したい場合 |
このように、目的や運用方法に応じて適切な助成金を選ぶことが、成功のカギとなります。
地方自治体の制度にも注目
都道府県や市区町村によっては、DX推進や人材スキル向上を目的とした独自の助成制度を設けている場合があります。
たとえば:
- 東京都:「DXリスキリング助成金」など、従業員に対するDX関連研修の費用を補助する制度を実施
助成金制度は毎年内容が更新されるため、制度内容・対象要件・期間・必要書類などを公式サイトで確認することが重要です。
助成金を使ったAI研修の申請手続きとスケジュール
助成金を活用して生成AI研修を実施するには、あらかじめ申請や書類の準備が必要です。制度の概要だけでなく、実際にどう手続きを進めればよいのかを理解することが、スムーズな受給につながります。
ここでは、申請前の準備から、申請・実施・報告に至るまでの一連の流れを具体的に説明し、スケジュールの管理や注意点も併せて紹介します。
申請前にやるべき3つの準備
助成金の申請前には、以下の3つの準備が重要です。
- 対象制度の選定と適合確認
研修の内容が、助成金制度の条件に適合しているかを確認します。生成AIに関する研修は、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」などが対象となることが多いため、研修内容と職務関連性が明確か、業務改善や生産性向上に直結する内容であるかを確認することが必要です。 - 研修計画の作成と講座内容の確定
助成金の申請には、事前に実施内容を具体化した研修計画書の提出が必要です。日程や講師、カリキュラム、対象従業員の人数なども明記する必要があります。また、職業能力開発推進者の選任や事業内職業能力開発計画の作成が必要になるため、事前に社内で調整・準備を進めておくとスムーズに申請ができます。 - 申請時に必要な書類の収集
就業規則、労働条件通知書、雇用契約書、給与台帳、受講対象者の在籍証明など、事前に用意する書類は多岐にわたります。早めに整備しておくことで、申請の遅れを防げます。
申請から受給までの5ステップを完全解説
助成金の申請から受給までは、以下のステップで進行します。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ステップ1 | 計画届の提出(研修実施の6か月前から1か月前までの間) |
| ステップ2 | 審査・通知(審査には通常2~3週間程度) |
| ステップ3 | 研修の実施(OFF-JTに該当する形式) |
| ステップ4 | 実施後の支給申請(研修終了後2か月以内) |
| ステップ5 | 支給決定・受給(申請後2~3か月程度で振込) |
研修開始前に申請が完了していない場合、助成金が不支給となる可能性があるため、スケジュールの管理が極めて重要です。
必要書類やスケジュール管理で気をつけること
助成金の申請や報告では、形式に沿った書類の提出と厳密なスケジュール管理が求められます。特に次のポイントに注意が必要です。
- 申請期限の厳守:計画届は訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間、支給申請は研修終了後2か月以内と定められています。
- 記録書類の保存:受講記録、受講者名簿、給与支払証明などは、一定期間保存する義務があります。
- オンライン研修のエビデンス確保:ログ記録や参加時間の証拠を残す必要があります。
こうした準備や管理が煩雑に感じる場合は、研修実施と申請支援を一括でサポートしてくれるサービスを活用することも有効です。
申請前にチェック!生成AI研修の助成金でよくある3つの落とし穴

助成金を活用すれば生成AI研修の費用を大幅に削減できますが、正しく理解していないと「申請したのに不支給」といった事態に陥る可能性があります。
ここでは、申請前に必ず確認すべき代表的な落とし穴を3つ紹介し、それぞれの対策を解説します。制度を正しく活用するための注意点を事前に押さえることが成功への第一歩です。
研修の内容・形式が条件に合っていない
助成金の対象となるには、「研修の形式」や「実施内容」が制度の要件を満たしている必要があります。たとえば、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」では、OJT(職場内訓練)は対象外で、OFF-JT(職場外訓練)でなければ助成対象になりません。
【対策ポイント】
- 講師の外部委託やオンライン形式でも、研修設計が計画的であることが必須
- カリキュラム、時間数、実施日程を具体的に明記する
実務に役立つ内容であっても、条件を外れていると助成金対象にならないので、専門家の監修や申請サポートを活用するのが効果的です。
受講タイミングと労働時間の取り扱いミス
研修の実施時間が、所定労働時間内なのか外なのかによって賃金助成の条件が異なります。労働時間外に研修を行うと、賃金助成の対象にならない可能性があります。
【対策ポイント】
- 勤務時間内に研修を組み込む
- 勤務時間外の場合は、事前に時間外労働として適切な手当を支給する計画を立てる
労働条件と研修実施の整合性が取れていないと不支給の対象となるため、就業規則の確認も必要です。
報告書や受講記録の不備による不支給事例
研修終了後に提出する報告書類に不備があると、助成金が支給されないケースがあります。たとえば、受講記録が不十分だったり、タイムスタンプがないといったことが理由になる場合もあります。
【対策ポイント】
- 出席簿、受講記録、研修報告書、写真やログ記録など証拠資料を完備
- 提出書類は記載ミスや不備がないよう二重チェック
提出する書類の内容が制度の要件と一致していないと審査に通らないため、記録管理を徹底する体制が必要です。
NBCインターナショナルのデジタル分野の研修/リスキリング支援のご案内

生成AIを活用した業務改善には、現場で実務を担う人材の育成が欠かせません。NBCインターナショナルでは、SEO対策やWEB広告運用に関する研修プログラムを用意しています。現役のコンサルタントが講師を務め、eラーニングやZoom研修により、最新の知識と実践力がバランスよく習得できる構成です。生成AIツールの活用方法について学べる研修プログラムも用意されています。
人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで、条件を満たせば受講費用の約80%が助成対象となります。以下に各講座の概要をご紹介します。
WEBサイトのデジタル分析技術習得講座
この講座では、SEO内部対策の原理とGoogle検索エンジンの構造を理解し、自社サイトの検索順位を向上させる方法を学びます。実際のWebサイトを題材に、構造化データや分析ツールの活用方法まで習得します。
【講座の特長】
- Googleのアルゴリズム理解
- サイト構造とメタ情報の最適化
- デジタル分析ツール(Search Console、GA4)の実演操作
検索順位が上がれば、広告費を抑えた自然流入の増加が期待でき、売上や集客に直結する効果が見込めます。
AIを活用したWEBコンテンツ制作のDX化講座
生成AIを活用して、キーワード調査から記事作成、改善・リライトまでを実演形式で学ぶ講座です。AIツールの選定や活用方法、SEO視点での文章最適化など、即業務に応用できるスキルを身につけられます。
【学べる内容】
- 生成AIツール(ChatGPTなど)の効果的な使い方
- ペルソナ設計と検索意図に応じた構成の作り方
- コンテンツSEOに適したライティング手法
コンテンツ制作の自動化と品質向上が同時に実現できるため、少人数体制でも多くの記事を量産可能です。
デジタルマーケティング運用・分析導入による販促DX化講座
この講座では、Google広告やMeta広告を使って、自社で広告戦略を立案・運用できる体制の構築を目指します。単なる知識習得にとどまらず、実演を通じた学習で社内運用スキルを養います。
【学べるスキル】
- リスティング広告とディスプレイ広告の基礎・応用
- 入稿・分析・予算配分の最適化
- 広告効果測定と改善のサイクル設計
広告の外注コスト削減に加え、PDCAを自社内で完結できるため、即応性のある運用体制を実現できます。
まずは資料ダウンロード・無料相談からご検討ください
NBCインターナショナルの研修は、SEOや広告運用のノウハウを社内に蓄積し、外注に頼らず自社でマーケティングを改善できる体制づくりを支援する実践型プログラムです。自社の担当者がスキルを習得することで、継続的な集客改善や施策のPDCAを自社内で回せるようになります。
また、人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで、条件を満たせば受講費用の約80%が助成されるため、コストを抑えながら社内人材の育成を進めることも可能です。
資料ダウンロードや無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
よくある不安や質問に答えます!助成金+AI研修Q&A

生成AI研修に助成金を活用する際、多くの中小企業が「自社も対象なのか」「オンライン研修でも大丈夫か」など、さまざまな疑問や不安を抱えています。
ここでは、特に多く寄せられる質問に対してわかりやすく回答し、安心して研修導入を進められるようサポートします。
本当に自社も対象?申請できる条件は?
中小企業であれば、ほとんどの業種が助成金の対象となります。助成金の多くは「中小企業基本法」に基づく規模基準に従っており、従業員数や資本金で判断されます。
【対象になる企業の例】
- 製造業、建設業、運輸業など:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
また、雇用保険に加入している社員がいれば申請可能なケースがほとんどです。まずは、自社の規模と制度の要件を照らし合わせて確認することが重要です。
オンライン研修でも助成金は使える?
はい、オンライン研修でも助成金の対象になります。ただし、以下のような条件を満たしている必要があります。
- 受講状況の記録(ログイン・ログアウト履歴、画面キャプチャなど)を提出できる
- 研修の開始・終了時刻が明確に分かる
- 講義がeラーニングまたは双方向型形式(Zoomなど)で実施される
eラーニングやZoomを用いた研修も、条件を満たせば問題なく助成対象となるため、地方企業や出張が難しい企業にも適した方法です。
申請しても却下されることはある?
申請しても却下される主な理由は、書類の不備や条件の不一致、記録不足などです。内容自体は制度に合致していても、形式的なミスによって受給が認められないケースがあります。
【よくある却下理由】
- 事前申請が遅れた(研修前の提出が必須)
- 就業時間と研修時間の整合が取れていない
- 受講記録・報告書の不備
事前に専門家へ確認し、書類や計画を丁寧に整備することで、却下リスクを大きく下げることが可能です。
まとめ
生成AI研修は、業務の効率化や人材のスキルアップを実現する中小企業にとって非常に有効な手段です。
しかし、その導入にはコストや申請の手間といった課題も伴います。そこで注目したいのが、人材開発支援助成金をはじめとする公的制度の活用です。適切な準備と正しい知識があれば、研修費用のおよそ80%を助成金でまかなうことも可能です。
ここで紹介したように、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」など複数の制度があり、自社の目的や社員構成に合わせて選ぶことができます。
また、研修の設計や申請書類の整備には注意点も多いため、申請サポートまで含めた研修サービスの活用が成功のカギとなります。
AI導入に足踏みしていた企業も、助成金の活用を前提にすれば初期コストを抑えつつ、戦略的にAI人材を育成できる道が見えてきます。
今こそ、自社のDX推進を現実のものにするチャンスです。自社に最適な研修計画の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
※本記事は助成金の受給を保証するものではありません。各助成金制度の内容・申請条件等は、公式サイト等で最新の情報をご確認ください。