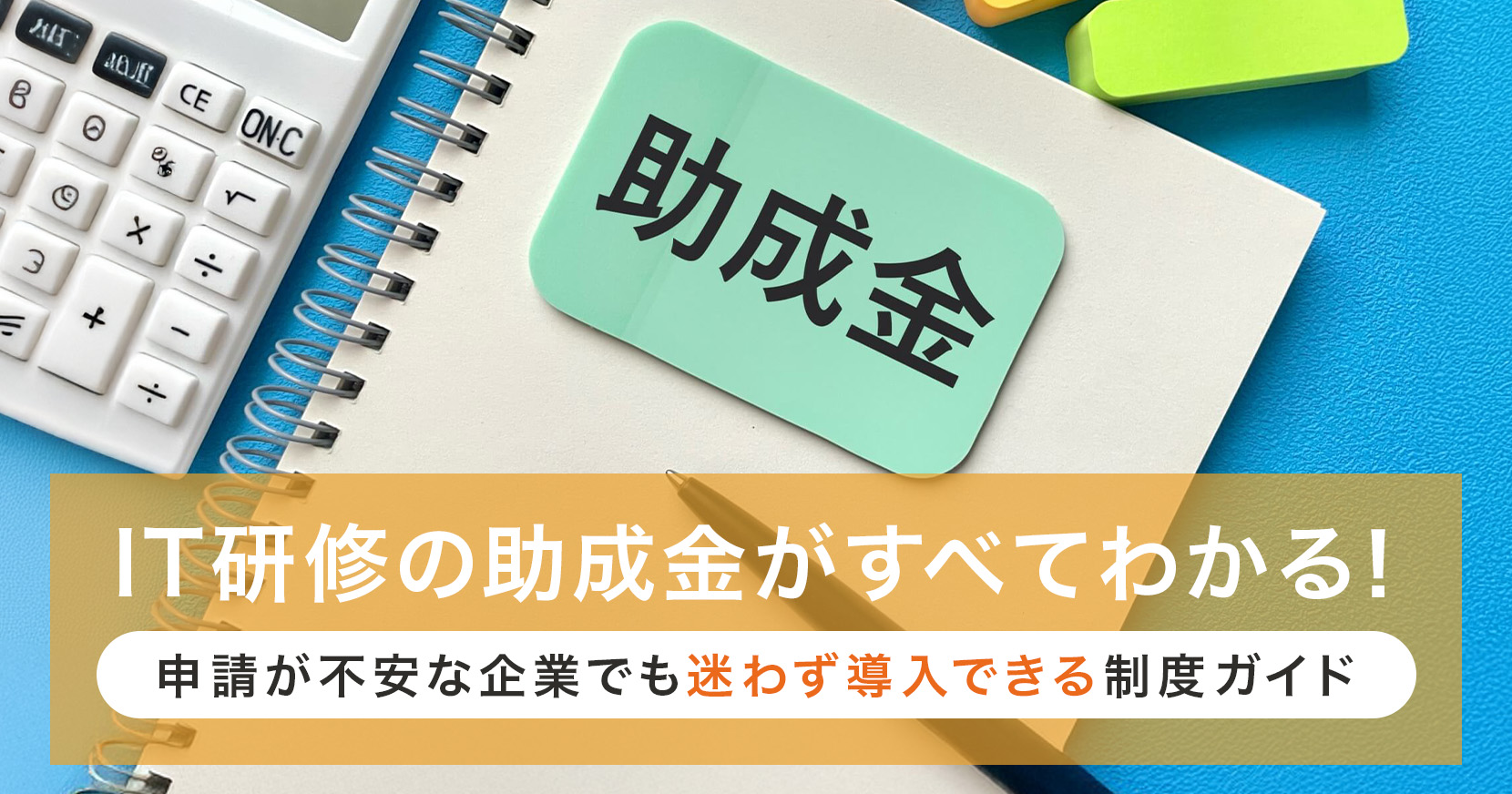目次
IT人材の不足やDX推進の必要性が高まる中で、多くの企業がIT研修の導入を検討しています。ですが「費用が心配」「申請が難しそう」と感じている中小企業の担当者も少なくありません。
この記事では、IT研修に使える助成金制度の種類や支給条件、申請手順までを網羅的に解説し、申請の不安を解消します。読み進めることで、自社に最適な制度の選定から申請・実施・受給まで、スムーズに進めるための知識が身につきます。
IT研修に助成金を活用するメリットと導入の基本
DXの加速や人材不足の深刻化により、企業にとってIT研修は必要不可欠な投資となっています。しかし研修の費用負担がネックとなり、導入に踏み切れない企業も少なくありません。ここでは、助成金を活用することで得られる経済的メリットや導入の基本的な考え方を解説し、制度活用の第一歩をサポートします。
なぜ今IT研修に助成金が注目されているのか
IT研修に助成金が注目されている最大の理由は、政府のデジタル人材育成政策が本格化していることにあります。リスキリングを推進する国家施策の一環として、多くの研修に対して経費助成や賃金助成が実施されているのです。
特に中小企業では、研修コストを削減しながら人材のスキルアップを図れるため、活用メリットが大きく、注目が集まっています。また、オンライン研修にも対応した制度が増えたことで、柔軟な研修設計が可能になり、地方企業でも導入しやすくなっています。
制度の多様化により、業種や企業規模に応じて選べる幅が広がっているのもポイントです。助成金を賢く利用することで、経営負担を軽減しつつ、競争力のある人材育成が実現できます。
DXや人材不足への対応として企業が取り組むべき理由
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、もはや大企業だけの課題ではありません。中小企業においても、デジタル人材の育成が急務となっています。しかし、IT人材の採用は困難を極めており、既存社員のリスキリングが現実的な解決策となります。
助成金を活用すれば、少ないコストで体系的な研修を実施できるため、従業員の離職防止や生産性向上にもつながります。とくに「人材開発支援助成金」や「DXリスキリング助成金」は、実務と直結したスキル習得が評価される制度であり、経営の成長戦略に直結します。
IT研修と助成金制度を組み合わせて導入することで、企業全体のデジタル基盤を強化し、市場環境の変化に柔軟に対応できる組織づくりが可能になります。
自社に最適な助成金を選ぶために知っておくべき制度一覧

IT研修に使える助成金制度は複数存在し、それぞれに適用条件や支給範囲が異なります。自社の研修内容や体制に最適な制度を選ぶことで、助成の受給率や金額に大きな差が生まれます。
ここでは代表的な助成金制度について、それぞれの特徴と適用のポイントを解説します。
人材開発支援助成金の各コース概要
人材開発支援助成金は、厚生労働省が提供する代表的な研修助成制度です。中小企業が自社の従業員を対象に、計画的な職業訓練を行う場合に賃金・経費の一部が助成されます。
本助成金の主なコースは以下のように分かれています。
| コース名 | 主な対象内容 |
|---|---|
| 人材育成支援コース | 職務関連知識・技能の習得訓練、OJT付き訓練、非正規から正社員化を目指す訓練 |
| 教育訓練休暇等付与コース | 有給教育訓練休暇制度の導入と取得 |
| 人への投資促進コース | デジタル人材・高度人材育成訓練、自発的訓練、定額制訓練等 |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 事業展開に伴う新分野技能習得訓練 |
支給要件としては、「計画届の事前提出」「所定出席率の確保」「適正な支給申請書の提出」などがあります。申請手続きや書類管理をしっかり行うことが成功の鍵です。
人材開発支援助成金(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
DXリスキリング助成金の特徴と適用条件
DXリスキリング助成金は、DX(デジタルトランスフォーメーション)に必要な人材を育成する企業に対し、支給している助成制度です。
対象研修には、クラウド、AI、IoT、セキュリティ、プログラミングなどの実務型スキル研修が含まれます。
- 東京都内に本社または主たる事業所を持つ企業が対象です
- 助成率は対象経費の4分の3、上限は1人1研修あたり75,000円です
- 申請企業あたりの年間上限は100万円です
事業のIT化や新規デジタル事業の創出を目指す東京都内の企業はこの助成金も活用できないか検討してみると良いでしょう。
DXリスキリング助成金(公益財団法人東京しごと財団):https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/skillup/skill-R7dx-risk.html
IT研修の種類と助成対象になる訓練内容
助成金の対象となるIT研修には一定の条件があります。対象となるのは、業務に関連したスキル習得や、職務能力の向上に資する訓練です。
ここでは、助成対象になりやすい研修の形態や内容について、具体的な例を交えて詳しく解説します。
OJTとOFF-JTの違いと対象になる研修とは
助成金制度では、研修の実施形態に応じて「OJT(On-the-Job Training)」と「OFF-JT(Off-the-Job Training)」の2つに分類されます。それぞれ助成条件が異なるため、違いを正しく理解することが重要です。
- OJT
業務中に上司や先輩が実務を通じて指導する訓練です。助成金の対象となるには、訓練計画や教育記録の作成、指導者の選任など、細かな条件を満たす必要があります。 - OFF-JT
社内外の研修機関による座学・オンライン講義など、業務とは切り離して行う訓練です。支給要件を満たしやすく、特にDXリスキリング助成金ではOFF-JTが必須要件となっています。
助成金制度の多くは、OFF-JTでの研修に対して経費助成と賃金助成の両方が支給されるため、制度活用を前提とした研修設計ではOFF-JTの導入が現実的です。
基礎スキルからマネジメントまでの研修コース例
助成金の対象研修は、業務に必要な知識や技能の習得が目的である必要があります。そのため、次のような研修コースが対象となることが多いです。
| 研修区分 | 内容の例 |
|---|---|
| IT基礎スキル研修 | OS、Office、クラウド操作、情報セキュリティ基礎など |
| 実務スキル研修 | Web制作、データ分析、業務システム操作など |
| 管理職向け研修 | DX導入計画立案、IT戦略策定、ITマネジメントなど |
企業の階層に応じた研修を用意することで、全社的なITリテラシーの底上げが可能になります。とくにマネジメント層向け研修は、DX施策の浸透に大きな影響を与えるため、助成対象になりやすい研修のひとつです。
ITリテラシー・プログラミング・データ活用研修の分類
助成金の対象になりやすい研修分野として、次の3つのスキル領域が注目されています。
- ITリテラシー研修
社内システムの正しい利用や情報セキュリティへの理解を深める研修で、全社員向けの導入研修に適しています。 - プログラミング研修
HTML、CSS、JavaScript、Pythonなど、業務で活用されるプログラミング言語の基礎を学びます。実務への応用度が高い研修が助成対象となりやすいです。 - データ活用研修
ExcelやBIツール、SQLを使ったデータ分析など、業務効率化や経営判断に直結するスキルを身につけます。
助成金を活用する際は、これらの研修が業務とどのように関係しているかを明示することが重要です。計画届には、その研修がどのような職務能力向上につながるのかを明確に記載する必要があります。
助成金申請で押さえておくべき流れと必要書類

助成金を確実に受給するためには、申請から受給までの流れを正しく理解し、必要書類の提出を漏れなく行うことが不可欠です。
ここでは、人材開発支援助成金を例に、最も重要な「計画届」「支給申請書」などの書類と手順を整理し、申請の失敗を防ぐためのポイントを解説します。
計画届の提出と事前準備の手順
助成金申請の第一歩となるのが、「計画届」の提出です。この届出は、「訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間」に管轄の労働局へ提出する必要があります。ここを怠ると、後からどれだけ要件を満たしても助成対象になりません。
準備の流れは以下の通りです。
- 対象者と研修内容の決定
- 計画届、訓練カリキュラム、就業規則(必要に応じて)を準備
- 労働局へ提出し、受理印をもらう
- 研修前に社内説明会などを実施して受講体制を整備
計画届には、訓練の目的、内容、対象者、期間、場所など具体的な計画を記載する必要があります。計画届は、提出後の修正が難しいため、内容の整合性や対象者の明確化が重要です。特にカリキュラムと勤務時間の整合性を確認するようにしましょう。
支給申請書の記入ポイントと注意点
研修終了後に行うのが「支給申請」です。研修終了日から2か月以内に、労働局へ支給申請書を提出する必要があります。記入ミスや漏れがあると、審査に時間がかかり、不支給となるリスクもあるため注意が必要です。
ポイントは以下の通りです。
- 記載内容は「計画届」と完全に一致させる
- 賃金台帳、出勤簿、研修記録を正確に添付
- 所定の様式を使用し、訂正印は避ける
支給申請時の必要書類
- 支給要件確認申立書
- 支給申請書
- 賃金助成・経費助成の内訳
- 訓練実施状況報告書
- 訓練経費の領収書や振込通知書の写し
- 出勤簿・給与台帳などの労働時間や賃金支払いの確認書類
また、オンライン研修など実施証明が難しい場合は、出席ログや課題提出記録を用意しておくことが重要です。書類の保存期間(5年間)も定められているため、保管体制も整えておく必要があります。
書類不備・出席率不足による不支給のリスク対策
助成金申請が却下される原因として最も多いのが、書類不備と出席率の未達成です。人材開発支援助成金では、原則として80%以上の出席率が求められています。
リスク対策としては、以下を実施してください。
- 欠席者の把握と理由の記録
- 出席率をリアルタイムで管理する仕組みの導入
- 書類のチェックリストを用いた二重確認
- 人事・経理担当者による申請前のクロスチェック
特に多い不備としては、「計画届との内容不一致」「賃金台帳のミス」「提出期限超過」などがあります。制度に沿った正確な運用を行い、書類整備を常に意識することが成功のカギです。
申請スケジュールと社内体制の整備ポイント
助成金を有効に活用するには、研修スケジュールに合わせた申請タイミングの把握と、社内での役割分担が必要です。また、制度改正への迅速な対応も求められます。
ここでは、申請をスムーズに行うためのスケジュール管理方法と体制整備のポイントについて解説します。
申請期限から研修実施までのスケジュール管理法
助成金の申請は、「計画届の提出」から始まり、「研修実施」「支給申請」に至るまで複数のステップがあります。各段階には明確な期限が定められているため、逆算したスケジュール管理が必要です。
人材開発支援助成金を活用する場合の代表的なスケジュール例は以下の通りです。
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 計画届の提出 | 訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間 |
| 研修実施 | 計画に沿って実施 |
| 支給申請書の提出 | 研修終了後2か月以内 |
この流れを守るためには、社内のカレンダーでリマインドを設定し、各フェーズに担当者を明確に割り当てることが重要です。また、繁忙期を避けた研修時期の選定も成功のポイントになります。
人事・経理・現場で役割分担を明確にする
助成金申請には、人事・経理・研修現場それぞれの連携が欠かせません。誰がどの書類を用意し、誰が提出手続きを行うかを明確にしないと、申請期限に間に合わなかったり、記載ミスが発生する可能性が高まります。
役割分担の例を以下に示します。
- 人事担当
対象者の選定、計画届の作成、研修カリキュラムの調整 - 経理担当
賃金台帳の整備、支給額の算出、支給申請書類の管理 - 現場責任者
出席状況の把握、実施記録の作成、研修後のフィードバック管理
これらを明文化した運用マニュアルを用意し、定期的な社内ミーティングで進捗管理を行うことがスムーズな運用に繋がります。
制度改正への対応と最新情報の収集方法
助成金制度は、年度ごとに条件や支給額が変更されることがあります。特にDXやリスキリング分野の制度は、政策動向により頻繁に改正される傾向があります。そのため、最新情報を正確に把握する体制の構築が欠かせません。
情報収集の方法としては以下が有効です。
- 厚生労働省の公式サイトや都道府県労働局の更新情報を定期確認
- 助成金専門のポータルサイトを活用
- 外部の社会保険労務士や研修機関と連携
制度改正に気づかず申請条件を満たせなくなるケースも多いため、常にアンテナを張っておくことが重要です。社内で担当者を決め、月1回程度の情報共有ミーティングを設けることを推奨します。
IT研修に助成金を使った企業の成功事例と失敗例
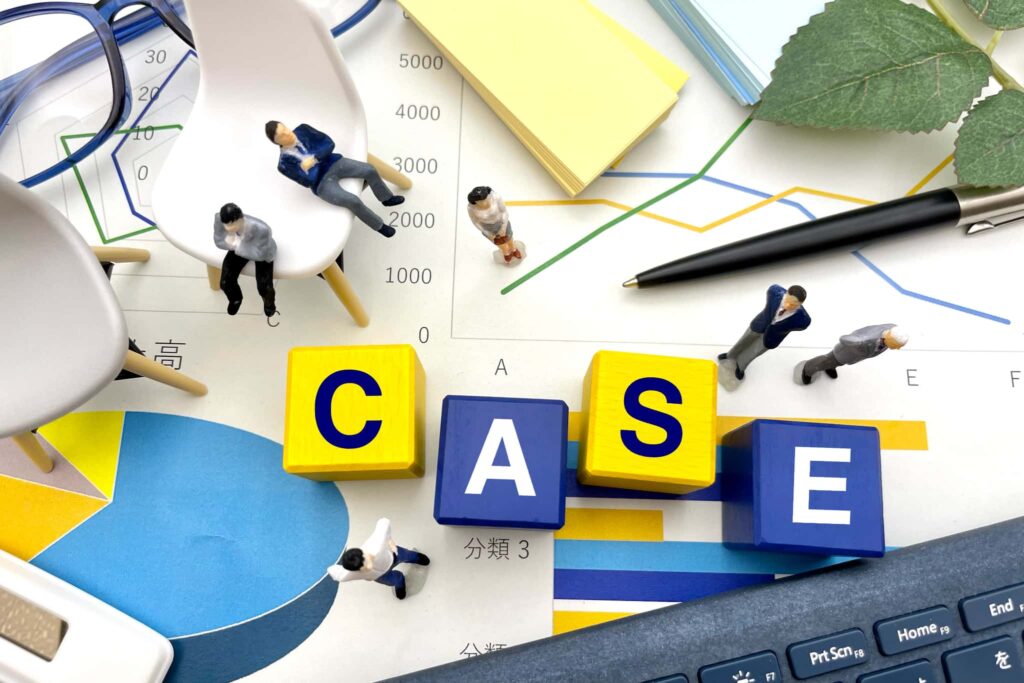
助成金制度の活用は、成功すれば研修コストの大幅削減と人材の成長を両立できますが、運用ミスによって不支給になる事例もあります。
ここでは、成功例と失敗例を通して、注意点や改善策、自社展開に役立つ視点を提供します。
成功例に学ぶ計画・実施・受給の流れ
ある中小企業では、「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」を活用し、新規事業立ち上げに伴うWEBマーケティング強化として外部機関のSEO研修の導入を決定。事前にしっかりと計画を立て、申請および研修受講を進めた結果、助成対象として認定を受け、経費助成と賃金助成を受けることができました。
成功要因は以下の3点です。
- 社内に助成金対応の専任担当を設けたこと
計画届の作成から申請スケジュールの管理までを一貫して対応し、期限や手続きのミスを未然に防止。 - 研修内容と事業展開の方向性を明確に紐づけたこと
新規事業としてのWebマーケティング強化という目的と、研修で習得するSEOスキルが業務でどう活かされるかを具体化し、制度要件への適合性を高めた。 - 研修後の業務設計や役割分担の見直しを実施したこと
研修受講後、担当者にSEO施策のPDCAを担う役割を正式に割り当て、研修内容が業務に反映される体制を整備したことで、助成金だけで終わらせない継続的な成果につながった。
よくある失敗と回避のヒント
一方で、助成金の申請に失敗した企業の事例では、以下のような問題が発生しています。
- 計画届の提出遅れ:研修直前に助成金制度の存在を知り、届出が間に合わなかった
- 出席率不足:繁忙期と研修時期が重なり、受講者の欠席が多発
- 申請書類の不備:計画届と支給申請書で対象者の記載に相違があった
これらの失敗は、事前準備の不足と制度理解の甘さに起因することが多いです。制度の基本ルールを社内で共有し、研修前に必ずチェックリストで確認を行うことが回避のポイントになります。
自社への展開に活かせるチェックポイント
成功と失敗の事例を踏まえて、自社で助成金を活用する際に意識すべきチェックポイントをまとめました。
- 計画段階で社内リーダーと外部パートナーを巻き込む
- 労働局とのコミュニケーションを事前に確保しておく
- 研修中の記録(出欠、成果物など)を丁寧に保管
- 制度変更に応じて柔軟にカリキュラムを見直す体制を整える
これらを実行することで、助成金活用の成功確率は大きく向上します。単なる「費用補助」ではなく、戦略的な人材育成の一環として制度を組み込むことが重要です。
IT研修と助成金を活用するためのチェックリスト

助成金を活用したIT研修の成功には、複雑な制度内容や多数の書類管理を効率的にこなす必要があります。ここでは、制度選定から申請、研修実施、受給までの流れを網羅的に確認できるチェックリストを用意し、抜け漏れのない準備と運用をサポートします。
制度・費用・期間の整理
最初に行うべきは、自社の状況に適した助成金制度の選定です。制度ごとに助成対象、支給率、申請方法が異なるため、比較表を作成して検討するのが効果的です。
各制度の要件に合致しているかを確認し、期間や費用の見積もりと合わせて整理することが重要です。
対象者・研修内容の一致確認
助成金の審査では、「対象者」「研修内容」「職務との関連性」が特に重視されます。制度要件と自社の研修設計が一致しているかをチェックしましょう。
- 対象者は雇用保険被保険者などの条件を満たしているか
- 研修内容が「業務能力向上」や「職務遂行スキル」として妥当か
- カリキュラムに「開始・終了時刻」「内容詳細」「受講スケジュール」などが明記されているか
- 訓練の実施方法(OJT/OFF-JT)が要件に合っているか
計画段階でこれらを明確化することで、申請の承認率が大幅に高まります。
準備・提出すべき書類一覧
助成金申請には多くの書類が必要となり、1つでも不備があると不支給のリスクが高まります。下記に代表的な書類をまとめました。
- 計画段階で必要な主な書類
- 計画届
- 研修カリキュラム
- 対象者リスト
- 就業規則
- 計画届
- 研修中・研修後に必要な主な書類
- 出勤簿・賃金台帳
- 研修記録(受講者の出席状況、成果)
- 支給申請書
- 支給額計算シート
- 出勤簿・賃金台帳
これらは電子データでも保管できるため、クラウド管理を活用して社内での共有体制を構築することが有効です。提出前には必ずダブルチェックを行いましょう。
NBCインターナショナルのデジタル分野の研修/リスキリング支援のご案内
IT・DXの推進には、現場で実務を担う人材の育成が欠かせません。
NBCインターナショナルでは、SEO対策やWEB広告運用に関する研修プログラムを用意しています。現役のコンサルタントが講師を務め、eラーニングやZoom研修により、最新の知識と実践力がバランスよく習得できる構成です。
人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで受講費用の約80%が助成対象となります。
以下に各講座の概要をご紹介します。
WEBサイトのデジタル分析技術習得講座
Webサイトの検索順位や成果改善につなげるための、内部対策・サイト解析の実践知識を体系的に習得できる講座です。
検索エンジンの仕組みや構造化データなどの基礎から、GA4やSearch Consoleなどを活用した分析・改善スキルまでを段階的に学べます。
- 内部対策の基礎/応用
- サイト解析と改善実践
- 検索順位低下の原因分析と対応策
習得できるスキル例:
- 検索エンジン最適化の構造的理解
- 内部対策の実践ノウハウ
- 最新のウェブ指標と分析ツール活用法
AIを活用したWEBコンテンツ制作のDX化講座
生成AIツールを活用して、SEOコンテンツ制作を効率化・高度化させるスキルを習得する研修です。
キーワード調査から記事構成、ライティング、アップロードまでを一貫して学び、AIを使ったライティング・リライト手法も実演で体得できます。
- コンテンツSEOの基礎〜実演
- AIツールを用いた制作DX
- キーワード選定やペルソナ設計の手法
習得できるスキル例:
- AIツールによるコンテンツ制作効率化
- ターゲットニーズに応える記事設計
- 実践的なキーワード選定・リライト技術
デジタルマーケティング運用・分析導入による販促DX化講座
広告配信の最適化とデータ分析による販促効果の最大化を目指す企業向け研修です。
リスティング広告・メタ広告の基礎から運用実演、分析による改善手法までを網羅し、広告運用人材の社内育成を目指す企業に最適です。
- リスティング・メタ広告の基礎/応用
- デジタル広告の効果検証と改善実践
- 最新の運用ツールを活用した販促DX
習得できるスキル例:
- 社内での広告運用体制の内製化
- データドリブンな広告改善スキル
- 広告ツールの活用による競争力強化
まずは資料ダウンロード・無料相談からご検討ください
NBCインターナショナルの研修は、SEOや広告運用のノウハウを社内に蓄積し、外注に頼らず自社でマーケティングを改善できる体制づくりを支援する実践型プログラムです。自社の担当者がスキルを習得することで、継続的な集客改善や施策のPDCAを自社内で回せるようになります。
また、人材開発支援助成金(リスキリング等支援コース)を活用することで、条件を満たせば受講費用の約80%が助成されるため、コストを抑えながら社内人材の育成を進めることも可能です。
資料ダウンロードや無料相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。
まとめ
IT研修に助成金を活用することで、中小企業でも低コストで高度な研修を導入できる環境が整っています。人材開発支援助成金やDXリスキリング助成金をはじめとした各制度には、それぞれに異なる支給要件や提出書類が定められており、事前準備の質が結果を左右します。
この記事では、制度選定から書類作成、研修実施、社内体制の整備に至るまで、各段階でのポイントを解説しました。
今後、自社でIT研修を実施しようと考えている企業は、助成金制度を単なるコスト削減ではなく、人材戦略の一部として活用する視点が求められます。この記事を参考に自社に最適な研修の導入と申請準備を進めてみてください。
※本記事は助成金の受給を保証するものではありません。各助成金制度の内容・申請条件等は、公式サイト等で最新の情報をご確認ください。