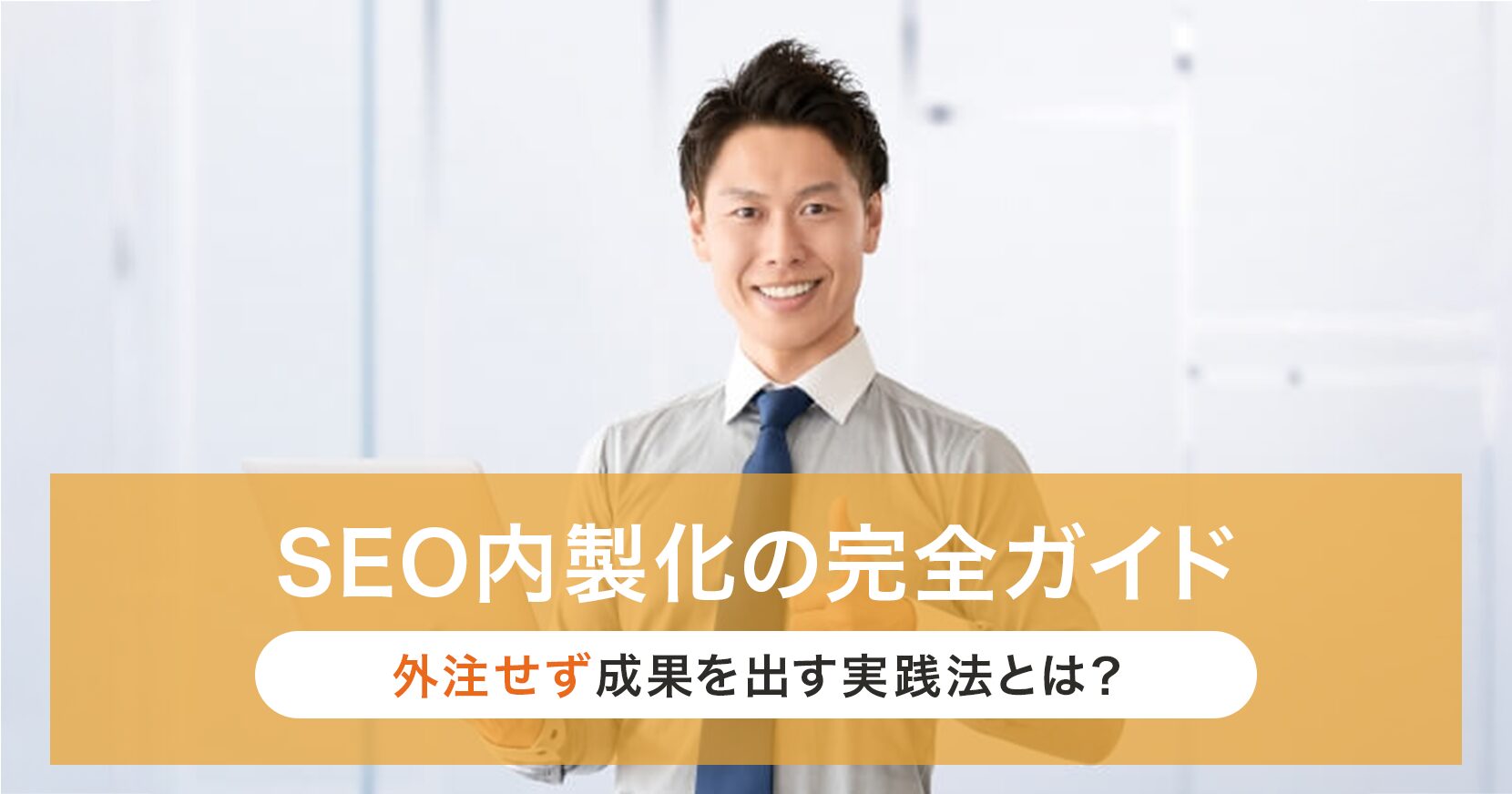目次
自社でSEO施策を運用する「SEO内製化」が、今、多くの企業に注目されています。外注に頼らず、自社の中でPDCAを素早く回し、戦略的なWeb集客を実現するこの手法は、特に中小企業やマーケティング予算を最適化したい企業にとって現実的かつ有効な選択肢です。
ここでは、SEO内製化の基本的な考え方からメリット・デメリット、体制作りのポイント、実行フロー、さらには社内稟議の進め方まで、内製化を成功させるために必要な知識とステップを詳しく解説します。
これを読むことで、自社に最適なSEO内製化の実行計画が描けるようになり、担当者として自信を持って提案・実行できる状態を目指せます。
SEO内製化とは何か?その基本と注目される背景
SEOの内製化は、単なる「作業の自社実施」ではなく、戦略設計から実行、改善までを自社で一貫して行う取り組みです。近年では、外注依存による柔軟性の欠如やコスト増加への懸念から、多くの企業が自社内でのSEO運用に切り替え始めています。
ここでは、SEO内製化とインハウスSEOの意味の違い、そして外注から内製に移行する動きが加速している背景について詳しく解説します。
SEO内製化とインハウスSEOの違いと意味を整理する
SEO内製化とインハウスSEOは同じ意味として語られることが多いですが、厳密にはニュアンスが異なります。
SEO内製化は、「SEO施策を外注せず、自社内で完結させる体制づくり」を指します。一方、インハウスSEOは「社内の担当者がSEO施策を直接担当する運用形態」であり、部分的な外注も許容するスタンスを含む場合があります。
両者に共通して重要なのは、社内に知見とリソースを確保し、持続可能な運用体制を構築することです。また、外注中心の施策では得られなかった「事業理解に基づいた戦略立案」や「高速なPDCA」が、内製化により実現しやすくなります。
このように、SEOの内製化は単なる作業移管ではなく、事業成長と連動するマーケティング体制そのものの変革とも言えるのです。
なぜ今、外注ではなく「自社でやる」SEOが求められているのか
SEOを取り巻く環境が大きく変化する中で、外注任せのSEO施策には限界があるという声が増えています。その理由は、以下のような背景に基づいています。
- Googleのアルゴリズムが高度化している
検索エンジンは、単なるキーワードではなく、「ユーザーにとって本当に価値のある情報」を評価する傾向が強まっています。そのため、業界知識に精通した自社のメンバーによるコンテンツ発信がより重要視されるようになっています。 - 外注によるスピードと柔軟性の欠如
施策の実施に時間がかかったり、戦略変更への対応が遅れることで、PDCAサイクルが回りにくくなり、成果が出づらくなるリスクがあります。 - コストと透明性に対する不安の増加
外注費が高騰する中で、実際にどのような施策が行われているかが見えづらい(ブラックボックス化)ことに対して、不信感を持つ企業が増えています。
こうした課題を踏まえ、自社で戦略と施策をコントロールできれば、以下のような長期的メリットが得られます。
- 予算を自社の中で効率的に使える
- ノウハウが社内に蓄積し続ける
- 社員のマーケティングスキルや理解が高まる
その結果、「社内でやるSEO」は単なるコスト削減手段ではなく、企業競争力を高める経営戦略の一部として位置付けられるようになっているのです。
こんな悩みがあればSEO内製化を検討すべき

SEO内製化はすべての企業に必要というわけではありませんが、特定の課題を抱えている企業にとっては非常に有効な選択肢になります。
ここでは、実際に多くの企業が抱える悩みをもとに、SEO内製化を導入するべきかどうかを見極めるポイントを解説します。
費用を抑えながらも集客を強化したい
外注SEOは高額な月額費用が発生することが一般的です。しかも、契約内容が不透明だったり、成果に直結しない作業にコストをかけてしまうケースも少なくありません。
その点、内製化すれば人件費やツール費用のみで運用できるため、費用対効果の高いSEOが実現できます。もちろん、初期段階ではノウハウやスキル習得の投資が必要ですが、中長期的にはコストを大幅に抑えつつ安定した集客基盤を築くことが可能です。
限られたマーケティング予算の中で最大の成果を狙う企業にとって、SEO内製化はコスト効率の高い集客戦略となります。
外注任せの施策に限界を感じている
「レポートは送られてくるが、実際に何をしているのかわからない」「改善提案が定型的で事業に合っていない」など、外注SEOに対する不満はよく聞かれます。
これは、自社の事業理解がない外部業者が施策を担当していることによる“戦略のズレ”が原因です。また、外注パートナーの意図を正しく評価できず、施策の質を判断する基準が社内にないことも大きな問題です。
SEOを内製化すれば、事業に直結したコンテンツや戦略をスピーディに実行できるようになります。担当者自らが状況を把握し改善の舵を取ることで、「現場感覚に合った施策」が進められるようになります。
社内にSEOノウハウがなく、育たないことに不安がある
「社内に知見がないから、SEOは外注しか選択肢がない」と考えている企業も少なくありません。しかし、これは逆に“自社内にノウハウがないことが最大の課題”とも言えます。
SEOを外注に任せてしまうと、その知識や戦略がすべて業者任せになり、社内には何も蓄積されません。結果として、担当者が異動・退職した際にゼロからのスタートになりやすく、マーケティング体制が脆弱になります。
一方、SEOを内製化することで、運用スキルや分析力、改善の視点が社内に蓄積され、再現性のある仕組みを持つことができます。これは、長期的なデジタル戦略において大きな資産となります。
SEOを内製化するメリットと社内にもたらす効果
SEO内製化には単にコスト削減という側面だけでなく、社内のマーケティング基盤を強化し、スピード感のある改善が可能になるという大きなメリットがあります。
ここでは、内製化がもたらす具体的な効果を掘り下げていきます。
外注費削減とスピード改善でPDCAが早く回る
外注に比べて、内製化は柔軟で即応性の高いSEO施策の実行が可能になります。施策の実施・改善を社内で行うことで、意思決定から実行までのスピードが格段に上がり、PDCAを高速で回すことができます。
また、外注にかかる費用を削減できるため、その分の予算をツール導入や人材育成に再配分することも可能です。PDCAが早く回ることで、「施策→効果測定→改善」というサイクルが定着しやすくなり、継続的な成果につながるのです。
ノウハウの蓄積が資産になり社内マーケが強くなる
SEOを内製化することで得られる最大の価値は、自社内にノウハウが蓄積されることです。外注では担当者が変わるたびに知見がリセットされがちですが、社内で運用すれば担当者間でのナレッジ共有が進み、マーケティングの地力が高まります。
たとえば、
- 成果が出た記事の企画・構成ノウハウ
- 特定の業界で有効だった被リンク戦略
- Googleのアップデートに対するリアルな反応と対策
などが、会社の知的資産として再利用可能になります。これは新しい施策の成功率を上げるだけでなく、外部に依存しない自走型のマーケティング体制を構築する鍵にもなります。
自社の事業理解に基づく戦略で精度が上がる
SEOの成果は単なるテクニックだけでなく、「誰に・何を・どのように伝えるか」というコンテンツ戦略に大きく依存します。自社の製品・サービスを熟知している社内担当者が施策を設計すれば、顧客課題にマッチしたキーワードやコンテンツを精度高く選定・作成することができます。
これは、外注では再現が難しい“事業理解に基づいたSEO”を実現するという意味で非常に重要です。
特にBtoB企業では、専門性の高い情報や業界特有のニーズに対応した記事が求められるため、社内での戦略設計が成果を左右する要因となります。
SEO内製化のデメリットとつまずく企業の共通点

SEO内製化は多くのメリットがありますが、導入すれば誰でも成果が出るというわけではありません。適切な体制と知識がないまま始めると、かえって非効率になったり、成果が出ずに頓挫してしまう可能性もあります。
ここでは、SEO内製化の代表的なデメリットと、実際に多くの企業がつまずくポイントを解説します。
SEOを理解する人材がいないと形だけになる
内製化を導入しても、社内にSEOの基本を理解している人がいないと、表面的な作業に終始してしまうリスクがあります。
たとえば、キーワードをなんとなく入れて記事を書いても、検索意図を満たせなければ順位は上がりません。また、Google Search ConsoleやGA4を正しく使えなければ、分析や改善も曖昧になります。こうした状態では、SEOを「実施しているつもり」でも実態は「形だけ」になってしまい、リソースを割いているのに成果が伴わないという悪循環に陥ります。
対策としては、最低限のSEOリテラシーを持つ人材の育成や、外部講座・勉強会の活用が有効です。初期段階で社内に知識を根付かせる仕組みを用意することが、内製化成功の前提になります。
業務過多・属人化で途中で止まってしまう
SEOは継続的に取り組むことで成果を生むマーケティング手法です。ところが、担当者に業務が集中したり、他業務との兼任で時間が取れなくなると、SEOの更新が止まってしまうケースが多く見られます。
特に中小企業では人手が限られているため、「1人の担当者に依存する体制」が続くと、その人が退職・異動したタイミングで運用が崩れてしまうという事態が起こりやすくなります。
この問題を回避するには、
- 複数名での分担体制
- 作業の手順化・マニュアル化
- タスク管理ツールの導入
などによって、属人化を防ぎ、運用を仕組み化することが求められます。
成果が出るまでに時間がかかると社内評価されにくい
SEOは広告のように即効性のある施策ではありません。一般的に成果が出るまでには数か月、場合によっては1年以上かかることもあります。この特性を正しく社内で共有できていないと、「結果が見えない=無意味」という評価を受けてしまい、継続のモチベーションや予算の確保が難しくなるリスクがあります。
この課題に対しては、中間KPIの設定やGoogle Search Consoleによる順位・流入の可視化、社内共有レポートの整備などで、「少しずつ前進している」ことを見せる工夫が重要です。また、あらかじめ上層部にSEOの特性を説明し、短期評価ではなく中長期視点での判断基準を共有しておくことが、成功への近道となります。
SEO内製化に向いている企業の特徴と体制の条件
SEOの内製化はどの企業にも当てはまるわけではなく、向いている企業には共通した文化や体制の特徴があります。ここでは、成功しやすい企業の条件や体制の整え方について解説します。
社内にWeb担当や情報発信の文化がある
SEOは継続的な情報発信と改善の積み重ねが求められるため、もともと社内にWebやコンテンツへの理解・関心があることが大きな強みになります。
たとえば、
- Webサイトを活用した営業・広報に前向きな風土がある
- ブログやニュースリリースの更新が定着している
- 社員の中にライティングや編集が得意な人材がいる
といった環境があれば、SEO施策への理解と協力が得やすく、スムーズに内製化を推進できます。情報発信に対する姿勢が受け身ではなく、「社内で伝える文化」があるかどうかが、内製SEOの土台となります。
少人数でもPDCAを回す意欲と体制がある
SEOに必要なのは人数の多さではなく、継続的にPDCAを回せる小さな体制と強い意志です。内製化に成功している企業の多くは、2〜3人の少人数チームでも、役割分担や定期ミーティングを設けることで、効果的なSEO運用を実現しています。
たとえば、
- 月1回の成果確認会議
- 各メンバーのタスク進捗の共有
- キーワード選定と記事制作の役割分担
といったミニマムな運用体制でも、PDCAを回す意識さえあれば内製化は可能です。大切なのは「続けることを止めない」マインドと習慣です。
継続的な評価・改善を支える体制作りができる
SEOは一度やって終わりではなく、継続して見直し、改善を繰り返すことで成果が積み上がります。そのためには、改善を促すための仕組みや役割分担が欠かせません。
内製化に向いている企業では、
- KPIの進捗を定期的に確認する会議体
- 分析結果を反映させる記事リライトの担当者
- CMSへのアクセス権限と更新ルールの整備
といった評価と改善のための仕組みが機能しており、SEOを「運用」として捉える力が備わっています。このような体制があれば、一度成果が出た後もその状態を維持・拡大しやすくなるため、安定したSEOの基盤が築かれます。
まず何から始める?SEO内製化の準備チェックリスト
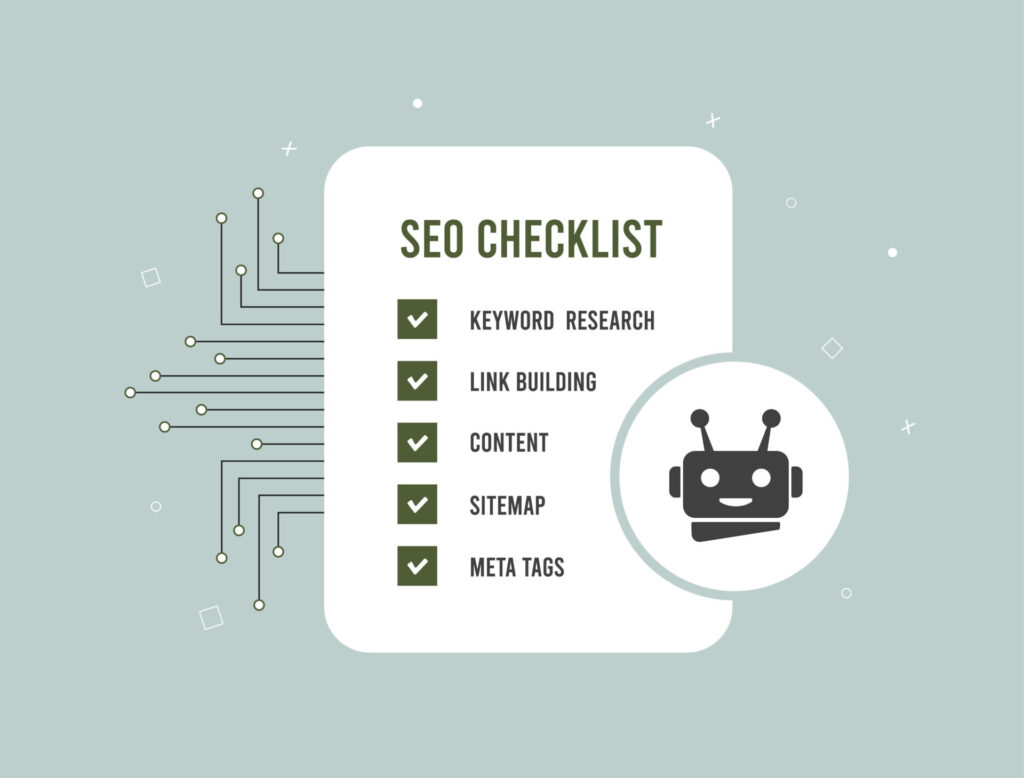
SEO内製化を成功させるためには、いきなり記事制作を始めるのではなく、適切な準備を段階的に整えておくことが不可欠です。
ここでは、SEOを自社運用するうえで、事前に確認しておきたいチェックポイントを3つの観点から整理しました。
キーワード選定・競合分析をできる人はいるか
SEOの出発点はキーワード選定と競合分析です。どんな検索語句を狙い、どのような競合がいるのかを把握しなければ、効果的な施策は打てません。
社内に以下のようなスキルを持つ人がいるかどうかを確認しましょう。
- キーワードツール(Googleキーワードプランナー、ラッコキーワードなど)の基本操作ができる
- 検索結果の上位記事を分析し、共通点や不足点を見つけられる
- ユーザーの検索意図を考慮して優先順位をつけられる
こうしたスキルはSEOの専門職でなくても、基本を習得すれば対応可能です。まずは社内に適任者がいるか、あるいは育成可能かを確認することから始めてください。
記事作成・CMS更新・分析など基本作業を誰が担うか
SEOを内製化する際に重要なのが、作業を担うメンバーの役割分担です。以下のようなタスクに対して、誰が、どのタイミングで、どのくらいの時間をかけて対応できるのかをあらかじめ明確にしておく必要があります。
| 作業内容 | 担当の例(理想) |
|---|---|
| 記事構成・執筆 | Web担当、営業部の知見者 |
| CMSへの投稿・調整 | 情報システム、Web担当 |
| タイトル・見出し調整 | ライター、編集担当 |
| GA4・GSC分析 | マーケティング担当、解析経験者 |
属人化しないよう、複数名で作業できる体制を作っておくことが大切です。作業の偏りをなくすことで、持続的な運用が可能になります。
効果測定・改善フローまで想定できているか
SEOは「作ったら終わり」ではありません。成果が出ているかを測り、改善に活かせるフローが整っているかどうかが、内製化の可否を分けるポイントになります。
以下の観点でチェックしましょう。
- GA4やGoogle Search Consoleの利用経験がある人がいるか
- どのKPI(検索順位、流入数、CV数など)を追うのか明確になっているか
- 定期的に効果を見直し、改善のアクションにつなげる仕組みがあるか
分析と改善が回らなければ、せっかく内製しても成果にはつながりません。「作る人」と「測る人」が連携し、成果を可視化する仕組みを設計しておくことが重要です。
SEO内製化を成功させる3ステップ実行フロー
SEOを内製化して成果を出すためには、やみくもに作業を始めるのではなく、段階を追って整備していくことが重要です。
ここでは、成功企業が実践している3ステップの実行フローをご紹介します。計画から運用までを一貫して社内で行うための流れを把握しましょう。
STEP1 戦略設計とKPIの設定
まずは、SEOを行う目的と狙う成果を明確にすることからスタートします。これが曖昧なままでは、施策の軸がブレてしまい、結果として効果の低い運用になります。
戦略設計では以下の点を明確にすることが重要です。
- どのペルソナに、どの段階でアプローチするか
- どんなキーワードを軸に、どのような導線でコンバージョンにつなげるか
- どのページを主軸にSEOを強化するか(サービスページ、ブログ、事例紹介など)
次に、KPIを数値化して設定します。たとえば、
- 検索順位:狙ったキーワードで10位以内を目指す
- 流入数:月間オーガニックセッションを◯件まで増やす
- CV数:SEO経由での問い合わせ数を◯件以上にする
といった形で、目標を明確にして進捗を評価できる基準を作っておきます。
STEP2 リソース確保と体制構築
次に行うべきは、実際に施策を実行するための体制を社内で整備することです。
必要なリソースには以下のようなものがあります。
| 必要項目 | 内容例 |
|---|---|
| 人的リソース | ライター、編集、解析、CMS更新担当など |
| 時間的リソース | 日々のSEO作業時間の確保 |
| 環境・ツール | GA4、GSC、キーワード分析ツールなど |
また、業務の属人化を避けるために、
- タスクのフローを文書化する
- 週次・月次の進捗確認ミーティングを設ける
- 外注と連携する部分がある場合はその役割を明確にする
といった体制構築が欠かせません。明確なルールと役割分担があるチームこそ、成果につながりやすくなります。
STEP3 運用・改善・社内浸透のサイクルを作る
体制が整ったら、いよいよ運用と改善のフェーズです。ここで大切なのは、施策の“打ちっぱなし”にならないよう、常に数値で評価し、改善につなげるサイクルを作ることです。
運用フェーズでは以下のようなアクションが必要です。
- 定期的にSEOレポートを作成し、KPIの進捗をチェック
- 流入や順位データをもとに、記事のリライトや構成変更を実施
- 成果事例や失敗事例を社内で共有し、チームの学びに活かす
また、SEOが一部メンバーの「業務」として終わらないように、経営層や他部門とも連携し、会社全体の取り組みとして位置づけることが内製化成功のポイントです。SEOを社内に根づかせ、持続可能な運用体制へと進化させることで、自社にとって最大の資産になるマーケティング施策となります。
SEO内製化に必要な業務とスキルセット

SEO内製化を成功させるには、単に記事を更新するだけでなく、戦略設計から実行・分析まで一連の業務を社内で担えるスキルセットが必要です。
ここでは、内製化に必要な具体的な業務と、それぞれに求められるスキルについて整理して解説します。
キーワード選定と競合分析
SEOにおいて最も重要な起点がキーワード選定と競合分析です。適切なキーワードを選べなければ、どれだけ良質な記事を書いても検索数は上がりません。
求められるスキルと作業内容:
- 検索ボリューム・競合性を見ながら適切なキーワードを選定する
- ラッコキーワード、キーワードプランナー、Ubersuggestなどのツールを活用できる
- 上位表示されている競合サイトの構成・特徴を分析し、自社との差別化ポイントを見極める
- 検索意図に沿ったコンテンツ企画の方向性を決める
ユーザーが何を求めて検索しているのかを理解し、それに応える形でキーワードを絞る能力が鍵となります。
コンテンツ企画・制作・リライト
SEOの成果は、質の高いコンテンツがあってこそ実現するものです。社内でのコンテンツ制作には、以下のようなスキルが求められます。
- 読者の課題を明確にし、構成を組み立てる企画力
- 専門的な内容をわかりやすく伝えるライティング力
- Googleの評価軸(E-E-A-T)や品質ガイドライン遵守を踏まえた記事制作
- 定期的なコンテンツのリライト・更新による情報の鮮度維持
ライティングが得意な社員がいない場合でも、企画と構成だけ社内で行い、執筆は外注ライターに任せるハイブリッド対応も可能です。
内部対策・被リンク・テクニカルSEO
内部SEOとは、サイト内部で行う検索順位向上のための構造的改善を指します。また、外部サイトからの被リンク対策や、ページ速度などの技術的改善もSEOに直結します。
必要な知識・業務:
- 適切なHタグ構造、メタディスクリプションの設定
- パンくずリスト、内部リンクの最適化
- モバイルフレンドリーや表示速度改善などのテクニカル対応
- サイテーションや広報活動によるナチュラルな被リンク獲得
これらは難易度が高いため、Web制作会社との連携や外部ツール活用が効果的です。全てを社内で行うのではなく、内製できる部分と外部に委託する部分を切り分ける視点が重要です。
Google Search ConsoleやGA4を用いた効果計測
施策の成果を正しく把握し、次のアクションにつなげるには、効果測定と分析スキルが欠かせません。
主に必要な作業と知識:
- Google Search Consoleで検索クエリや表示回数、CTRを確認
- GA4で流入経路、ページごとの滞在時間やCVを測定
- KPIに対する達成状況を可視化し、次のアクションに活かす
- リライトやリンク追加など、データを根拠にした改善施策の実行
分析は継続すればするほど仮説の精度が上がり、より成果につながる施策が打てるようになります。
外注と内製のハイブリッドも視野に入れる
すべてを社内だけで完結させるのが理想とは限りません。自社のリソースやスキルに応じて、内製と外注をうまく組み合わせる「ハイブリッド型運用」つまりインハウスSEOは、柔軟かつ現実的なSEOの選択肢です。
ここでは、内製と外注のバランスを取るための考え方と、効果的な支援活用術をご紹介します。
内製できる業務と外注した方が良い業務の切り分け方
すべてを内製化しようとすると、時間・知識・人材の面で限界が生じます。そこで、どの業務を社内で担い、どこを外部に頼るかを明確にすることが大切です。
一般的な切り分けの例は以下のとおりです。
| 業務項目 | 内製向きの業務 | 外注先の業務 |
|---|---|---|
| キーワード選定 | 社内の顧客理解を活かす | 専門ツールでの分析支援 |
| コンテンツ企画 | 自社の業界知識や強みを活かした企画 | リサーチ支援・構成チェック |
| 記事作成 | 社内リソースで対応可能なら内製 | ライティング経験豊富な外注ライター |
| CMS更新 | 日常的な運用は内製 | 複雑な修正や開発は制作会社に依頼 |
| テクニカルSEO | 基本は制作会社と連携 | 表示速度改善・構造化データ対応など |
社内で価値を発揮しやすい部分に集中し、専門性が求められる箇所だけを外部に依頼するのが、効率的なハイブリッド運用のポイントです。
部分的な支援活用でコスト・成果のバランスを取る
ハイブリッド運用は、コストを抑えながら外部の専門性を活かす手段として非常に有効です。たとえば以下のような形での支援が考えられます。
- 月1回の戦略レビューやキーワード選定のサポート
- 記事構成テンプレートの作成支援
- CMSのテンプレート修正やSEOプラグイン設定のアドバイス
- GSC・GA4のデータ分析と改善提案
これらは、継続契約ではなくスポット対応でも依頼できるケースが多く、柔軟に利用することが可能です。「必要なときにだけ専門家の知恵を借りる」という選択が、コストと成果のバランスを高めるカギになります。
属人化しない体制構築のための支援活用術
外部パートナーを活用する際に重要なのが、支援内容を“担当者依存”にしない工夫です。属人化すると、その担当者が抜けたときに施策が止まる危険性が高まります。
属人化を避けるためのポイント:
- すべての業務を手順書やドキュメントとして社内共有する
- 定例ミーティングやレポートを通してナレッジを可視化する
- 支援会社との窓口を1人に絞らず、複数名で情報共有する
- 担当交代時にも引き継げる仕組みを整える
また、支援先の選定時には、「ノウハウを社内に残す姿勢のある会社かどうか」を確認することが非常に重要です。
SEO内製化を社内で提案・稟議する際の伝え方と資料例

SEOの内製化を進めるには、上層部の理解と承認を得るための提案活動が欠かせません。社内稟議を通すには、単なる「費用削減」の話にとどまらず、戦略的な投資であることを明確に伝える必要があります。
ここでは、稟議を通すための資料の作り方や、説得のための視点を解説します。
稟議を通すためのメリットとコスト比較資料の作り方
内製化提案の第一歩は、外注と内製それぞれのコストとメリットを明確に比較することです。上層部は「ROI(投資対効果)」を重視するため、金額ベースでの比較が効果的です。
比較の視点:
| 項目 | 外注SEO | 内製SEO |
|---|---|---|
| 月額コスト | 数十万円必要なことが多い | 人件費+ツール費 |
| 施策スピード | 確認・調整に時間がかかる | 社内完結で即日対応可能 |
| ノウハウ蓄積 | 外注先に依存、社内に残らない | 社内に継続的に蓄積 |
| 成果への理解 | 戦略が見えにくいことがある | 事業理解に基づく施策で精度向上 |
このような表に加えて、1年間の試算やシミュレーションを資料に加えると、説得力が高まります。
成果シミュレーションとKPI設計の考え方
SEOは成果が短期で見えにくいため、中長期視点での成果モデルを提示することが重要です。上層部の不安を払拭するには、「どれくらいで、何が、どう変わるのか」を可視化しましょう。
成果シミュレーションの例:
- 3か月後:検索流入が10%増加
- 6か月後:10記事が上位表示され月間CVが5件増
- 1年後:問い合わせ数20%増加、広告費を削減
これらに対して、KPIとして何をどこまで追い、どのように報告するかも資料に明記すると、上層部に安心感を与えることができます。また、「PDCAをどう回すか」「誰がどの作業を担当するか」など、具体的な実行フローを設けると承認率が格段に高まります。
上層部の不安を解消するQ&Aと説得ポイント
内製化を提案すると、「本当にできるのか?」「リソースはあるのか?」「成果が出る保証は?」といった不安の声が上がるのが通例です。これに対しては、よくある質問と回答の形で事前に備えておくことが有効です。
想定される質問と回答例:
- Q:SEOの専門知識が社内にないが大丈夫か?
- A:初期段階では専門家のアドバイザー支援を活用し、段階的にスキルを社内に移管します。
- A:初期段階では専門家のアドバイザー支援を活用し、段階的にスキルを社内に移管します。
- Q:リソースが不足しているが本当に運用できるか?
- A:1記事あたり週2〜3時間の作業からスタート可能で、属人化を避けた役割分担体制を整えています。
- A:1記事あたり週2〜3時間の作業からスタート可能で、属人化を避けた役割分担体制を整えています。
- Q:広告よりも成果が見えにくいのでは?
- A:定期的なサーチコンソールレポートやKPIで進捗を可視化し、短期・中長期での成果を分けて説明可能です。
- A:定期的なサーチコンソールレポートやKPIで進捗を可視化し、短期・中長期での成果を分けて説明可能です。
経営層の視点は「リスクと費用対効果」にあります。感情論ではなく、データとロジックで不安を丁寧に解消することが説得のコツです。
NBCインターナショナルのSEO研修サービスのご案内
NBCインターナショナル株式会社では、SEO施策の内製化を目指す企業様向けに、実務に直結する研修サービスを提供しています。現役のSEOコンサルタントが講師を務め、検索上位表示に不可欠な内部対策や、集客につながるコンテンツ制作のノウハウを、座学と演習を組み合わせたカリキュラムで体系的に学べます。
特に特長的なのが、生成AIを活用したSEOコンテンツ制作手法が学べる点です。キーワード設計から構成案作成、記事ライティング、リライトまで、AIを業務にどう取り入れるかを実務目線で解説。社内の制作業務を効率化・高度化したい企業様にも最適です。
さらに、本研修は厚生労働省の「人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)」を活用することで研修費用の最大75%の経費助成と賃金助成(1時間あたり960円)を受けることが可能です。
コストを抑えながら、外部依存から脱却し、自社内でSEO運用を回せる体制づくりを支援します。
※本助成金は令和8年度に終了予定のため、ご検討中の企業様は早めのご相談をおすすめします。
研修はeラーニングとオンライン講義のハイブリッド形式で、全国から柔軟に受講可能。
「SEOを自社で回せるようにしたい」「施策のスピードと精度を上げたい」――そんな企業様は、ぜひこちらから一度お問い合わせください。
まとめ
SEO内製化は、単なるコスト削減ではなく、自社のマーケティング基盤を強化し、持続可能な成長を目指すための戦略的な取り組みです。
ここでは、SEO内製化の基礎から、導入のメリット・デメリット、必要な体制やスキル、実行フロー、さらには稟議の通し方まで網羅的に解説してきました。
中でも重要なポイントは、事業理解に基づく戦略設計と、社内での継続的なPDCA運用が成功の鍵になるということです。SEOを「仕組み」として内製化することで、外注に頼らずとも高い成果を上げることが可能になります。
マーケティング担当者として、SEO内製化の全体像を把握し、社内での提案や実行計画を具体化できれば、企業の競争力を高める大きな一歩となります。